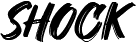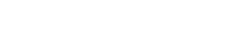
Radio Program

The Forefront of the Space Industry.
宇宙関連産業最前線
市場規模は270兆円へ!ビジネス機会の創出に乗り遅れるな!
Special Guest:AOKI HIDETAKA
スペシャルゲスト:青木 英剛さま / 一般社団法人Space Port Japan 理事
ー 本日は「宇宙大罪」をテーマにお話を伺います。スペシャルゲストとして、一般社団法人Space Port Japan 理事であられる青木英剛さまをお迎えしています。そしてアストロゲート株式会社 代表取締役の大出大輔さまにもお越しいただいております。青木さん、大出さんよろしくお願いします!早速ですが大手さんと青木さんの出会いについてお聞かせいただけますか?
大出)
青木さんと初めてお会いしたのは2018年、内閣府主催の宇宙ビジネスアイデアコンテスト「S-Booster」で、私がファイナリストになったときです。その際、青木さんはメンターや審査員として活動されており、そのご縁で出会うことができました。
その後、私自身がスペースポートの取り組みを進めていること、そして青木さんも特にスペースポート関連の活動に力を入れていらっしゃることから、これまで非常によくしていただきながら、さまざまな取り組みをご一緒させていただいています。
ぜひ、青木さんから自己紹介いただいてもよろしいでしょうか?
青木)
改めまして、青木英剛と申します。現在、非営利の一般社団法人「スペースポートジャパン」の創業者であり、理事を務めています。私は「宇宙エヴァンジェリスト」という肩書きで活動しており、これが私のメインの宇宙における取り組みとなっています。
「エヴァンジェリスト」という言葉はIT業界ではおなじみかもしれませんが、日本語では「伝道師」にあたります。私は宇宙ビジネスの可能性を多くの人々に伝えることを仕事としており、国内外で講演やイベント登壇を通じて宇宙ビジネスの魅力を発信しています。また、新たに宇宙分野へ参入しようとする企業や自治体、あるいはスタートアップを立ち上げようとする方々への支援も行っています。これまで多くの宇宙ベンチャーや大企業の参入を支援し、その背後でサポート役として活動してきました。
さらに、JAXAや内閣府などの宇宙関連の政策に関わる委員としても活動し、政策面での支援も並行して行っています。
私がこうした仕事に至った背景ですが、もともとは宇宙船の設計者としてキャリアをスタートしました。アメリカで航空宇宙工学を学び、修士課程を修了後に日本へ帰国。国際宇宙ステーションの物資補給船「こうのとり」や、2023年に月面着陸に成功した月着陸実証機「SLIM(スリム)」の設計・開発に技術者として携わりました。
このように、技術者としての視点や宇宙ものづくりの経験をバックグラウンドに持ちながら、現在はビジネスや政策の分野にも関わり、技術・ビジネス・政策の3つを統合する形で多方面から宇宙産業の発展を後押ししています。
ー まず、リスナーの皆さんに「宇宙とは何か」について少し考えていただければと思います。現在の宇宙技術やビジネスの進展、そして私たちがどこまでその可能性を広げているのかについて、可能な範囲でぜひご紹介いただければと思います。よろしくお願いいたします。
青木)
現在の宇宙産業の市場規模は2023年の統計データによると60兆円を超えています。この規模は半導体や医療機器の世界市場と同程度であり、すでに非常に大きな市場が形成されていると言えます。さらに、最新のデータでは2035年には市場規模が270兆円に達すると予測されています。これは現在の日本のGDPの約半分に相当する規模感で、宇宙産業が今後急速に成長していくことを示しています。
現在の60兆円の市場規模の多くは主に放送通信分野と位置情報分野に支えられています。放送通信分野では、テレビの生中継や飛行機内Wi-Fiなど人工衛星を利用した通信サービスが中心で、この分野だけでも何十兆円規模の市場が存在しています。一方、位置情報分野では、GPSを利用したカーナビや電車・飛行機の運行管理、物流の追跡などが含まれます。これもまた数十兆円規模の巨大市場となっています。これら二つの分野がこれまで宇宙産業の中核を担ってきたと言えます。
今後、60兆円が270兆円に膨れ上がる中で特に成長が見込まれる分野として宇宙インターネットと宇宙ビッグデータがあります。宇宙インターネットについては、世界中にはまだ30億人以上がインターネットにアクセスできない状況があり、この課題に取り組むためにSpaceXなどが進めている「宇宙からインターネットを提供するプロジェクト」が注目されています。この分野は今後、最も大きく成長すると考えられています。
宇宙ビッグデータについては、地球観測衛星を活用して地球の詳細なデータをリアルタイムで収集・提供する分野です。現在のGoogle Earthのデータは数年遅れですが、これが毎日更新されるようになれば、新しいビジネスチャンスが生まれるでしょう。このような宇宙由来のデータを活用する市場が今後急成長していくと見られています。
現状の宇宙産業はすでに巨大な市場を形成しており、これからの成長においても通信やデータ活用といった新たな分野が牽引役となることが期待されています。

ー 宇宙ビッグデータという言葉は、実は今日初めて耳にしました。少し調べてみたところ、人工衛星に搭載されたカメラやセンサーで地球上の状況をモニターし、そのデータを解析することで、災害対策や環境保全、経済活動、SDGsといったさまざまな分野で活用できるデータのことを指すとありました。この認識で間違いないでしょうか?
青木)
おっしゃる通りです。宇宙ビッグデータをイメージしやすい例として、「監視カメラを宇宙に置いてしまおう」という発想がわかりやすいかと思います。宇宙には国境がありませんので、監視カメラのような人工衛星を打ち上げれば、好きなときに好きな場所を好きなだけ撮影することができます。
こうして宇宙から撮影されたデータは、企業の意思決定や災害時の情報提供など、さまざまな場面で活用されています。たとえば、災害が発生したときには瞬時に撮影されたデータをもとに救援活動に役立つ情報を提供することが可能です。
さらに、地上のビッグデータ、たとえばインターネットや工場から得られるデータと組み合わせることで、宇宙データとの相乗効果が生まれます。これにより、企業や政府の意思決定がより的確に行われるようになり、さまざまな分野での活用が広がっています。
私はこの衛星の画像データを「神の目」と呼んでいます。上空から自由に地球を俯瞰する視点は、まるで神様が見ているような感覚を与えます。この「神の目」を活用することで、ビッグデータによる意思決定の精度が飛躍的に向上し、社会全体に革命を起こしつつあると感じています。宇宙ビッグデータの可能性は非常に大きく、これからの発展が楽しみです。
ー 大出さんはどうお考えですか?
大出)
宇宙ビジネスはみなさん遠いと感じる方もいらっしゃると思いますが、人工衛星の画像は天気予報の予測精度の向上に使われていますし、GPSもみなさん活用されていると思います。人工衛星データの活用は、近年多くの分野で注目を集めています。青木さんの視点から見て、特に面白いと感じた事例は何でしょうか。
青木)
宇宙産業は、ものづくりの会社だけでなく、幅広い分野の企業に新たなビジネスチャンスを提供しています。人工衛星を製造する企業にとっては典型的なものづくりビジネスですが、人工衛星から得られた画像の解析となると、AI企業やソフトウェア企業など、宇宙とは直接関係のない分野の企業にも大きな可能性が広がります。
最近では、人工衛星の画像を活用する解析事業者が増えています。例えば、Spacataという企業は、人工衛星から取得した画像をAIを用いて自動処理し、3DのCGデータを生成する技術を開発しています。このデータをもとに、メタバース空間やデジタルツインが自動で構築されます。
この技術により、自治体は災害シミュレーションに活用し、ゲーム会社は街を舞台にしたゲームを開発するなど、多岐にわたる用途が生まれています。Google Earthのような既存のバーチャルデータもありますが、商業利用には著作権の制限があります。それに対し、Spacataのデータは自由に活用できる点がビジネス面での大きな強みです。
このような先進的な取り組みを支える企業の多くは、宇宙産業の出身者ではなく、ソフトウェアエンジニアや連続起業家など異業種の専門家たちです。彼らの挑戦が、宇宙データビジネスの可能性をさらに広げています。
ー 青木さんが宇宙に興味を持ったきっかけや感動したエピソードはありますか?
青木)
私が宇宙に興味を持ったきっかけは、宇宙飛行士の毛利守さんが宇宙に行かれたテレビ番組を見たことでした。宇宙関連の仕事をしている方々には、幼少期に宇宙への憧れを抱いたエピソードが多いと感じます。アポロの月面着陸を見て宇宙に夢を持ったり、ガンダムのプラモデル作りがきっかけで宇宙船に興味を持ったりする人もいます。
最近では、若い世代が宇宙ビジネスに興味を持つ動機も変わってきました。イーロン・マスクのような宇宙企業家に憧れ、自分もそのような道を目指す学生が増えています。私自身も中高生向けに宇宙起業家論の講義を行っていますが、彼らの関心の高さに驚かされます。
ー 宇宙ビジネスの将来について、現在有効な手段や新しい取り組みが多く模索されています。この分野と結びつけられる可能性のある方法について、ご意見をお聞かせください。
青木)
宇宙ビジネスの広がりは、かつてのIT産業の成長に似ていると感じています。ITがかつて多くの企業の業務効率化を支え、今やインターネットが日常生活に溶け込んでいるように、宇宙技術も将来的にはすべての企業が当たり前に活用する時代が来るでしょう。
気象観測やGPS、宇宙インターネットなど、すでに私たちの知らないところで宇宙技術は活用されています。今後はさらに多くの分野に広がり、企業の競争力を支える基盤となると確信しています。
私の使命は、宇宙技術の可能性を広める“宇宙エヴァンジェリスト”として、あらゆる企業や業界に宇宙ビジネスの価値を伝えることです。お土産屋さんやレストラン、町工場など、どの業界にも宇宙技術の導入のチャンスがあります。すべての企業が宇宙技術を取り入れる未来を目指して、これからも活動を続けていきます。

ー 以前は宇宙分野といえば、技術者やエンジニアのための領域という認識が強く、大学で設計技術を学んだり、企業で技術経験を積んだ人が進む道と考えられていました。しかし、最近ではその風潮が大きく変わり、幅広いバックグラウンドを持つ若者が宇宙ビジネスに興味を持つようになっていますよね?
大出)
宇宙ビジネスは今や幅広い職種の人々が必要とされる、一般的なビジネス分野になりつつあります。最近、ミラノで開催された国際的な宇宙展示会では、宇宙ベンチャー企業がプラダとコラボして宇宙服を開発するなど、技術者だけでは生まれにくい独創的なアイデアが実現されました。このように、多様な分野の専門家が参加することで、宇宙ビジネスはさらに広がり、ビジネスチャンスも増えていくと感じています。
青木さんは幅広い宇宙産業に精通されていますが、その中でも特にスペースポートジャパンの理事を務めるなど、スペースポート分野に注力されている印象があります。現在のスペースポートの状況や、青木さんがこの分野に取り組むことになった経緯について、ぜひお聞かせいただければと思います。
青木)
スペースポートとは、宇宙空間にある施設ではなく、地球上に設置される宇宙航空のインフラです。多くの人は「宇宙ビジネス」というと、宇宙そのものに行くことを思い浮かべがちですが、実際には地上のインフラであるスペースポートがその出発点となります。
飛行機で海外旅行に行く際に空港が必要なように、宇宙に行くためにはスペースポートが不可欠です。スペースポートは、ロケットの打ち上げだけでなく、宇宙旅行や衛星の運用など、宇宙産業全体を支える重要な拠点です。
スペースポートジャパンでは、「スペースポートを制する者が宇宙を制する」という強いメッセージを掲げ、スペースポートの重要性を訴えています。スペースポートが整備されることで、ロケット産業が活性化し、人工衛星の運用や宇宙旅行の需要も増加し、さまざまな宇宙ビジネスが生まれていくと考えています。こうした背景から、スペースポートへの注力が始まりました。
いま、航空業界では、韓国のインチョン空港やシンガポールのチャンギ空港が世界的な航空物流のハブとして成功を収めています。一方で、日本の羽田空港や成田空港は、その競争に遅れを取ってしまいました。このような状況を踏まえ、宇宙分野では日本がアジア圏の宇宙への玄関口となることを目指す必要があります。
現在、アメリカは多くのスペースポートを持ち、宇宙開発の最前線を走っています。ヨーロッパや他の地域でも同様の取り組みが進んでいますが、アジアにおいては、どの国が宇宙への入り口を担うかが重要な課題となっています。
日本がアジアの宇宙ハブとなるためには、宇宙への出発点としてのスペースポートの整備が不可欠です。すでに日本国内では複数のスペースポートプロジェクトが進行中であり、これらは世界に誇れる取り組みといえるでしょう。
ー 日本は地理的優位性があるというようなお話も伺ったのですが、いかがでしょうか。
青木)
ロケットの打ち上げには、地理的な条件が大きな影響を与えます。ロケットはしばしば隣国の上空を飛ぶため、国際的な安全性や外交的な配慮が求められます。
例えば、韓国からロケットを打ち上げる場合、日本の上空を通過する可能性があり、安全上の懸念から日本が反対することがあります。そのため、韓国でのロケット打ち上げは非常に難しい状況です。
一方、日本は四方を海に囲まれているため、ロケットを北、南、東のいずれの方向にも安全に打ち上げることができます。唯一、西への打ち上げは、地球の自転に逆らうため効率が悪く、燃料の消費が増えるためほとんど行われません。
西にロケットを打ち上げる国として知られているのはイスラエルだけで、地理的な制約と安全保障の理由から例外的な存在です。他の国々は主に海に向かって南、北、東へと打ち上げを行います。
このような条件を考えると、広い海が東側にある国として、アメリカ、ブラジル、ニュージーランド、そして日本がロケット打ち上げに適した国といえます。
さらに、ロケット打ち上げの地理的優位性を活かすためには、適切なスペースポートの整備が重要です。日本のように海に囲まれた国では、東側の広い海域を利用することで、安全な打ち上げルートを確保できます。このため、日本国内では複数のスペースポートプロジェクトが進行中であり、これらは将来的な宇宙ビジネスの成長を支える重要な基盤となるでしょう。
ー 青木さんの視点から見て、世界のスペースポート開発の現状はどのようになっているのでしょうか。日本がこの分野でリードする可能性について、今後の展望をお聞かせください。
青木)
現在、世界中でスペースポートの誘致競争が激化しており、既存のスペースポートや計画段階のものを含めると約100か所が存在します。特にアメリカは進んでおり、連邦航空局(FAA)の許認可を受けたスペースポートが約14か所、許認可外の私有地も含めると約20か所あります。たとえば、アマゾン創業者のジェフ・ベゾス氏は個人保有の牧場からロケットを打ち上げています。
日本でも8つのスペースポートプロジェクトが進行中で、アメリカ、中国、ロシア、ヨーロッパなどと競い合っています。今後の競争力のカギは、打ち上げの容易さ、海へのアクセス、宇宙関連のサプライチェーン、そして滞在環境の魅力です。
スペースポートの運営には、数か月にわたるロケット打ち上げ準備期間が必要であり、その間の滞在環境が重要な選定基準となります。滞在する技術者のためのホテルや飲食施設、快適な生活環境が求められます。
日本は美味しい食事、ホスピタリティ、豊かな自然、生活のしやすさなど多くの魅力を備えており、技術者に選ばれるスペースポート候補として非常に有利な立場にあります。これらの要素を活かし、日本は今後のスペースポート市場で世界的な競争力を発揮できると期待されています。
ー 非常にワクワクする、興味深いお話をありがとうございました!