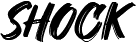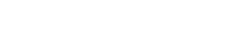
Radio Program

Democratizing the universe through digital.
デジタルを通じて宇宙を民主化
誰もが宇宙開発に参入し宇宙を利用する時代がやってくる!
Special Guest:KATAYAMA TOSHIHIRO
スペシャルゲスト:片山 俊大さま / 株式会社スペースデータ 執行役員CMO 一般社団法人スペースポートジャパン 共同創業者・理事
ー 本日はスペシャルゲストに株式会社スペースデータ 執行役員CMO、一般社団法人Space Port Japan 共同創業者、理事の片山俊大さまをお迎えし、アストロゲート株式会社 代表取締役 大出大輔さまとともにお送りしていきます。片山さん、大出さんよろしくお願いします!
大出)
スペースデータさんに片山さんが参加されたのは驚きでしたが、まずスペースデータさんがどのような会社なのか、そして片山さんがどのような経緯でジョインされたのか、ぜひ教えていただけますか。
片山)
どんな会社かを説明するのは少し難しいのですが、スペースデータさんは「宇宙をインターネットのように身近に」というスローガンのもと活動している会社です。誰もが宇宙開発に参画でき、誰もが宇宙を利用できるような世の中を目指しています。最終的には、宇宙の民主化を実現したいと考えている会社です。
大出)
スペースデータさんが扱っているデジタルツインが非常に印象的です。具体的には、どのようなコンテンツがあるのか、また視聴者がイメージしやすい事例などがあれば教えていただけますか?
片山)
宇宙産業の中で一番大きな分野は実は人工衛星関連なんです。人工衛星は基本的にデータビジネスで、皆さんがよく目にする天気予報や、GPSを使ったGoogleマップなども、そのデータの一部です。ただ、そのようなデータを使うのは簡単ではありません。
そこで、私たちはデジタルツインを活用して、誰でも簡単に宇宙データを扱えるプラットフォームを作っています。デジタルツインとは、現実の地球をそのまま仮想空間に再現する技術です。例えば、新宿やトンガ王国などをデジタル空間に再現することで、ゲーム開発、映像制作、街づくり、さらには災害対策など、さまざまなユースケースに応用できます。
このプラットフォームを使えば、宇宙を意識せずに直感的に宇宙データを利用できるようになるというサービスを展開しています。
大出)
実際の世界では、災害が起こってみないと分からなかったようなことを、デジタル空間上で街を再現し、シミュレーションの中で災害を発生させて検証することができます。その結果、どんな問題が起こるのか、どこにリスクがあるのかを事前に把握し、対策を講じることができるようになるというわけですよね。
片山)
例えば「このくらいの災害が起きたらどうなるか」や、「この場所にビルを建てたらどうなるか」といった、現実では簡単に実験や変更ができないことをデジタルツインで再現し、シミュレーションできます。これによって、さまざまなユースケースが生まれています。
さらに、デジタルツインの技術をそのまま宇宙に応用しています。宇宙ステーションや月面をデジタルツイン化することで、地球にいながら宇宙の実験やシミュレーションが可能になります。これまでは、JAXAやNASAなどとデータをやり取りしながら進める必要があり、参入障壁が非常に高かったのですが、それを大幅に下げることができます。
さらに、シミュレーションだけではなく、その先のものづくりにも活用しています。たとえば、ロボット開発や宇宙ステーション向けのOSの導入です。このOSは、WindowsやiOSのような統一規格の宇宙版で、これにより多くの人が開発に参加できるようになります。さらには、アプリケーションを通じて宇宙産業に関わりのない人でも新しい利活用方法を考えられるような世界を作っています。
大出)
片山さんがスペースデータの取り組みに参画されることになった背景や経緯について、ぜひお聞かせいただけますか。
片山)
私がスペースデータに参画したきっかけは、代表の佐藤航陽とのご縁です。佐藤はメタップスの創業者であり、「お金2.0」や「世界2.0」などのビジネス書を手がけたベストセラー作家でもあります。今年7月、日本最大級のビジネスカンファレンスであるIVS京都で、パネルディスカッションに一緒に登壇したのが初めての接点でした。
その後、親しくなる機会が増え、そのご縁から9月にスペースデータの執行役員として参画することになりました。
大出)
デジタルツインを使って宇宙とさまざまなものをつなぎ合わせるという取り組みは、片山さんがこれまで携わってきた活動とも非常に関連性がありそうだと感じます。そのあたりについて、これまでのご経験や取り組みと、現在のお仕事との結びつきについて教えていただけますか?
片山)
実は非常に神話性があると感じていますし、同時に私がこれまで感じていた課題意識とスペースデータの取り組みがピタリと合致していると思います。私自身、これまで約20年、電通でマーケティングやブランディングに携わってきました。宇宙との関わりは、中東で石油権益を確保する際に、宇宙産業を提供することで石油を安定供給するという外交戦略に携わったのが最初です。
その後、スペースポートジャパンで宇宙港(スペースポート)の実現に向けた活動を行いました。スペースポートとは、宇宙に行くための地上拠点で、日本語で言うと「宇宙港」です。私はそのスペースポートの周辺での街づくりや経済圏づくりにも携わってきました。
つまり、これまで「宇宙」と「宇宙以外の産業」をつなぐ活動を続けてきたんです。宇宙とエネルギー産業、宇宙と地上の土地、宇宙と経済圏の掛け算を通じて新たな産業づくりに取り組んできました。しかし、個人の力だけでこれを大きな事業に育てるのは難しい部分がありました。
そんな中で、デジタル技術やプラットフォームの考え方を活用し、これらを一気に体系化して背景化できるスペースデータの取り組みは、まさに私が抱えていた課題にピタリとはまるものでした。そうした経緯から、「ぜひ一緒にやりましょう」という形でスペースデータに参画しました。

大出)
現在、宇宙のデータを活用するには、人工衛星を打ち上げるだけでも莫大なコストがかかり、取得した人工衛星データも非常に高額なため、まだ利用が難しい面があります。しかし、スペースデータさんのプラットフォーム化の取り組みによって、これらがより手軽に使えるようになり、結果として宇宙データの普及が大きく進む、という流れにつながるということですね?
片山)
そうですね。1900年代後半に、ものづくり産業がIT化され、インターネットによって世の中が大きく変わったのと同じような流れを宇宙産業でも作れたらと考えています。現在の宇宙産業は、まだものづくり中心で、市場主義的な側面が強く、かつての家電業界に近い状態だと思っています。
そこにプラットフォーム発想やソフトウェアの考え方、オープンアーキテクチャのようなアイデアを取り入れることで、宇宙業界にソフトウェアやプラットフォームを提供し、インターネットのように誰もが普通に使える世界を目指しています。たとえば、インターネットではプログラミングやプロトコルの知識がなくても、直感的に利用できるようになっていますよね。同じように、宇宙も誰もが簡単に直感的に使え、さらに開発にも参加できるような社会を作っていきたいという考えです。
ー インターネットは生活に欠かせない存在となり、医療や福祉では電子カルテやスマートフォンで利用者の状況を把握するなど、大きな恩恵を受けています。同様に宇宙産業でも、近未来に向けた技術が進んでいます。それどころか、すでに実現していることもあるんですよね。
片山)すでに実用化が進んでいて、GPSだけでなく、インターネット通信そのものが宇宙でどんどんインフラとして構築され、利用されています。そのため、望むと望まざるとに関わらず、誰も宇宙と無縁ではいられなくなってきているのが現状です。
ー ここで片山さんのご紹介をさせていただきます。片山さんのご著書『超速でわかる!宇宙ビジネス』では、現状の宇宙航空建設の状況をコンパクトに解説し、宇宙ビジネスがいかにあらゆる業界にとって必須のビジネス教養になっているかを示されていて非常に興味深い内容でした。本書の内容をリスナーの皆様にもご説明いただけますでしょうか?
片山)
今、宇宙ビジネスが盛り上がり、「自分も何かやってみたい」と思う方が増えていますが、参入はもちろん、概要を知るだけでもハードルが高いんですよね。さらに、「これ以上簡単に書けない」と言われる本でも、実際にはかなり難しく感じられることが多いです。宇宙は、一生をかけて追求するような極めて優秀な方々が活躍している分野なので、誰にでも分かりやすく伝えるのは難しいところがあります。
私の著書『超速でわかる!宇宙ビジネス』は、宇宙業界外の視点を活かし、ほとんど絵や図解で構成する形で、これ以上ないほど分かりやすくまとめました。歴史から未来、宇宙工学、エンターテインメント、エネルギービジネスまで、幅広いジャンルに関して解説しており、入門書として最適な一冊になっていると思います。
大出)
片山さんは幅広い視点で宇宙を見ておられ、著書も手がけていらっしゃいますが、個人的に「この領域×宇宙は特に面白い」と感じていることや、注目している分野があればぜひ教えてください。
片山)
まず言いたいのは、宇宙って上空100キロ以上の場所を指すんですが、実は軽井沢から東京までの距離よりも宇宙の方が近いんです。つまり、宇宙は「すぐそこ」にあるわけで、宇宙と地球を切り分けること自体がもはやナンセンスな時代になりつつあります。
すべてのビジネスが宇宙とつながる可能性を持っており、それがまさにインターネットと似ている部分ですね。昔、インターネットが登場した際に「何が変わるの?」と聞かれて「全部だよ」と答える人がいたように、宇宙ビジネスも同じで「何が変わるの?」と聞かれたら「全部だ」と答えたいです。
その中で、個人的に注目しているのは「アート×宇宙」です。たとえば長野は海に面していないので宇宙港をつくるのは難しいですが、美しい星空があり、それに関連してアートの可能性が広がる地域だと思っています。そもそも宇宙に行くこと自体がアートに近いとも言えますし、アートは希少性が求められるものです。宇宙での体験や、宇宙から見た地球のような視点をアートに昇華することで、新しいビジネスが生まれると考えています。
実際に私も、いくつかアート作品のプロデュースに関わっているので、「アート×宇宙」は特に面白い分野として注目しています。
例えば、現在私が携わっているアートプロジェクトの一つとして、国際宇宙ステーション(ISS)の外に設置されているアート作品があります。その作品がもうすぐ地球に戻ってくる予定なんです。この作品を活用した新しいアートプロジェクトを展開していきたいと考えています。
プロジェクトのタイトルは「ミクロコスモス」です。これを通じて、宇宙とアートを融合させた新たな試みを世の中に届けたいと思っています。今後の展開にご期待いただければ幸いです!

大出)
面白いですね。片山さんはもともと宇宙業界以外のご経験から宇宙に関わるようになったわけですが、今宇宙に取り組んでいる方々には、宇宙好きの方が多い印象があります。片山さんご自身には、そういった「宇宙好き」という感情や興味はもともとあったのでしょうか?
片山)
実は、ほとんど「宇宙好き」という感情はありませんでした。先ほどお話ししたように、エネルギーや石油関連の仕事をしていたときに、偶然宇宙に関わる仕事に縁があったのがきっかけです。そのときは1回限りのつもりでしたが、そこからいろいろ広がり、気づけば今でも宇宙にしっかり取り組んでいるという状況です。
もともと宇宙に対して好き嫌いの感情は特になく、「上空100キロを超えた空間に対して、好きも嫌いもないだろう」というのが私の感覚でした。ですから、必要に応じて軽々と越えていくべき存在というイメージに近いですね。
大出)
そうですね。これから新規事業を考える上で、宇宙を絡めながら本業を成長させたいと考える方は確実に増えていると思います。むしろ、宇宙を特別視するのではなく、必要に応じて柔軟に活用する目線の方が、こうした取り組みを進める上で非常に重要だと感じますね。
片山)
今では通信業界、エンタメ、物流など、あらゆる産業が宇宙との掛け算を始めています。その際に重要なのは、「宇宙じゃない産業」が主語になることです。彼らにとっては本業が中心であり、そこに宇宙を取り入れることで成功の可能性が広がる、という視点が大切です。逆に、宇宙を主軸に物事を進めると、途中で何かしらの歪みが生じやすいんですよね。
だから私は自分のことを「宇宙業界の邪内法芸人」と呼んでいます。このような立ち位置が、実際に多くのニーズに応えていると感じており、このポジションで活動させていただいているという形です。
大出)
いち早く宇宙をうまく活用するために、この配信を聞いている方々がどのような行動を取るべきか、またどんなことに気をつけていればいいのか、片山さんのお考えをぜひ教えてください。
片山)
難しい質問ですが、今はあらゆるものがパラダイムシフトしており、業界の垣根が壊れ、「何か×何か」の掛け算がどんどん増えている時代だと思います。視野を広く持ち、常識にとらわれず「これとこれを掛け算したらどうなるだろう?」と考える柔軟な発想が求められています。
さらに視野を広げると、最終的には宇宙視点にたどり着くと思うんです。よく「木を見て森を見ず」と言いますが、森を見るには人工衛星、つまり宇宙視点が必要になりますよね。広く世界を見渡すスタンスを持つことで、自然と宇宙との掛け算が生まれてくるのではないでしょうか。
ー まだまだ現実には難しいかもしれませんが、宇宙×介護のような未来があるのではないかと考えたんです。無重力空間で介護を行うことができたら、それは究極の介護かもしれない、と。これから技術が進歩していく中で、宇宙産業や宇宙ビジネスは、他の分野と切り離せない関係になっていくのではないかと、個人的にも感じています。
片山)
宇宙×介護については、2つの視点があると思います。まず、最近では昔と違い、体を悪くした方や高齢者の方が宇宙旅行に行くケースが増えています。宇宙旅行といっても10分程度の短時間のものですが、そういった旅行に行く方が増えているんです。残された人生の中で宇宙に行き、自分が何を考え、何を感じるのかを体験するという形で、クオリティ・オブ・ライフを向上させるために宇宙を選ぶ方が一定数います。
もう一つは、介護ロボットについてです。現在、介護ロボットはまだ人間がやった方がいい部分が多いと言われていますが、介護のために開発されたロボットは、実は宇宙で大いに役立つ可能性があります。その理由は、宇宙飛行士の時給が非常に高いため、可能な限りロボット化したいというニーズがあるからです。人間がやる必要のない仕事をロボットに任せることで効率化が図れます。
地球上ではまだ実用化が進んでいない介護ロボットを、宇宙で先に実用化するという視点も十分に考えられると思います。
ー 宇宙が私たちの生活とつながり、新たな可能性を広げていく未来に大きな希望を感じました。本日は貴重なお話をありがとうございました!