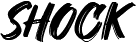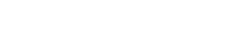
Radio Program

The Future of Healthcare Transformed by Public Relations.
広報で変わる医療の未来
「優しい病院広報の教科書」に学ぶ地域医療のブランディング
Special Guest:YAMADA TAKASHI
スペシャルゲスト:山田 隆司さま / NPO法人メディカルコンソーシアム ネットワークグループ 理事長
ー 本日はイノベーションをどう社会に発信していくのか、広報PRという観点について詳しくお話を伺ってまいります。本日のスペシャルゲストはNPO法人メディカルコンソーシアムネットワークグループ 理事長 山田隆司さんです。NPO法人メディカルコンソーシアムネットワークグループのホームページを拝見しました。そこには「病院広報を研究する」とあります。医療や福祉の広報は難しく、どのように発信すればよいのか悩む方も多いのではないでしょうか。
そうですね。解決策はあると思いますが、まだまだ課題は多いですね。
特に、広報そのものを十分に理解されていない方が多いことが問題です。例えば、「広報」と「広告」の違いが曖昧だったり、情報を発信すればすぐに反応があると誤解していたりするケースがよく見られます。そのため、すぐに成果が出ないと「効果がない」と判断して、広報活動をやめてしまうことも少なくありません。結果として、広報の取り組みが定着せず、形にならないことが多いのが現状です。
しかし最近では、大手メディアが病院広報に関するアワードを開催するなど、医療系メディアが積極的に関わるようになりました。こうした取り組みによって、病院広報への理解が少しずつ広まりつつあると感じます。
ー 先生のご著書『地域に伝えたい!やさしい病院広報の教科書』は、分かりやすく具体的な事例も多く、大変参考になりました。また、メディカルコンソーシアムネットワークグループの活動も拝見しました。病院は距離を感じやすい存在ですが、地域にとっては大きな安心につながるものです。そのため、広報・PRには特殊なアプローチが必要だと感じます。効果的な広報やブランディングのポイントについてどのようにお考えでしょうか?
特に特殊なことをする必要はないと思います。
広報とは、病院の誇大広告をすることではなく、地域の方々に安心してもらえる医療情報を提供することです。例えば、病院の特色や提供する医療の内容、もし入院が必要になった際の環境など、そうした情報を少しずつ伝えていくことが大切です。
重要なのは、これを継続的に行い、経営計画の一環として位置づけることです。その方向性と病院が掲げる理念を照らし合わせながら発信を続けることで、病院自体が情報とともに成長し、地域にとってより信頼される存在になれるのではないかと考えています。
ー 病院の役割としては、患者を受け入れ、治療を行い、地域に戻すことが基本ですよね。そのため、「地域とのつながりを積極的に持つことは病院にとって負担が大きい」と考える方もいるかもしれません。しかし、現在の時代の流れとしては、病院が地域に開かれた存在であることが求められている、という理解でよろしいでしょうか?
そうですね。ご存知のように、各病院にはそれぞれの役割があります。
例えば、急性期病院は急性期の治療を行い、その後の療養環境に応じて他の病院へ転院するという流れが一般的です。患者さんが適切な治療を受けるためには、病院の役割を明確にし、次の受け入れ先がどこにあるのかをしっかり伝えることが重要になります。
そのため、病院同士の連携を強めながら、地域の方々に「どの病院がどのような役割を担っているのか」を理解してもらうことが大切です。いざという時に、患者さんが適切な病院を選べる環境を整えることこそが、広報の役割だと思います。

ー 病院の中で広報という仕事は、医療とは少し異なる立ち位置にあるように思います。専門職の方々と一緒に仕事をする上で、難しさを感じることもあるのではないかと思うのですが、その点についてはいかがでしょうか?
これは、病院や医療法人が広報をどう位置づけるかによって、広報の役割が大きく変わると思います。
戦略的に広報を行っている病院では、医療者と広報担当者の情報交換が活発に行われるようになってきています。また、医療者側から「この情報を発信してほしい」という要望が広報に届くことも増えています。
広報の役割は、院外だけでなく院内のコミュニケーションも含まれるため、医療者との相互理解を深めながら情報を発信していくことが大切です。ただし、その関係を築くには時間がかかり、簡単ではありません。
しかし、広報の部署がしっかり機能し、継続的に活動を続けていくことで、徐々に医療者との信頼関係が築かれ、効果的な情報発信が可能になると考えています。
ー これまでの活動の中で、印象に残っている広報の成功事例や、すぐに実践したくなるような事例があれば、ぜひお聞かせください。
広報の手段として広報誌を作ることは非常に重要だと考えています。
今はSNSが主流になっていますが、しっかりとした広報誌を作ることで、病院の情報を家庭に届けることができます。私が活動してきた中でも、広報誌の記事が本になったり、記者クラブに届けた広報誌を見た記者が取材に来たりと、さまざまな広がりが生まれました。
また、広報誌には地域の情報も取り入れることが大切です。例えば、病院の周りのお店やNPO法人の活動を紹介することで、病院と地域とのつながりを強めることができます。単に「病院の取り組みを伝える」だけでなく、地域を巻き込んだ広報誌を作ることで、コミュニケーションのきっかけが生まれるんですね。
今、お手伝いしている病院でも、ゼロから広報誌を始めたことで、地域のお店や商工会議所など、病院とは一見関係のなさそうな組織ともつながりが生まれています。広報誌は単なる情報発信ではなく、地域との関係を築く重要なツールになり得ると感じています。
ー 「地域にこういう病院があるのは嬉しい」と感じることで、より深いコミュニケーションが生まれていくのだと思います。広報誌を作るという思いがあり、実際に動いていくことで、地域全体が一つになっていく。今お話を伺って、まさにそういう形が広がっているのだと感じました。
こうした取り組みは一度で完結するものではなく、何度も重ねていくことが大切なんですよね。
繰り返し発信し続けることで、コミュニケーションが深まり、つながりが強くなっていきます。そうした関係性の中で、お互いに依頼し合うことが増えたり、新しい仕事が生まれたりすることもあります。
結果として、地域との関係がより広がり、深まっていくという流れができていくんですよね。
ー 先生はこれまで、病院の特徴や魅力を伝える広報の成功事例を数多くご覧になられてきたと思います。もしご開示いただける範囲で、具体的な事例を教えていただければと思います。
広報誌を作る際には、さまざまな記事を掲載しますが、特に医療記事をしっかり作ることが重要です。
例えば、疾患に関する記事なら、疾患の解説や予防法を含め、ドクターに監修してもらいながら正確な情報を提供することが大切です。また、それだけでなく、先生がなぜその診療を始めたのか、なぜ在宅医療に関わるようになったのかなど、医師の想いや背景を伝える記事を加えることで、読者の関心を引きやすくなります。
医師という存在は、患者にとって話しづらい、距離があると感じられることも多いですが、記事を通じて医師の人となりを伝えることで、患者が「初めて会う感じがしない」「親しみを感じる」と思うこともあります。これは、心理学でいう「ラポール(信頼関係)」を築く効果があり、結果として、診察時のコミュニケーションがスムーズになることもあるんです。
また、病院にとっては「集患」よりも「選ばれること」が大切だと思います。一般の方は「集患」という言葉にあまり良い印象を持っていません。そうではなく、患者が自ら選びたくなる病院とは何かを意識し、そのための情報発信を行うことが、広報として重要な視点だと考えています。

ー 広報誌というと、どうしても雑誌や紙媒体をイメージしがちですが、デジタル版の広報誌も同時に作った方がよいのでしょうか?
そうですね。以前は紙媒体の広報誌が主流でしたが、今は個人が自ら検索して情報を得る時代になりました。そのため、デジタルを無視するわけにはいきません。
特にホームページの充実は非常に重要です。最近は、病院のホームページも検索しやすく、見やすく進化してきています。例えば、「内科を受診したい」と思ったときに、ホームページ内に診療科別のボタンが配置されていて、直感的にアクセスできるなどの工夫がされています。
また、SNSの活用も年齢層ごとに適切な媒体を選ぶことが大切です。例えば、高齢の方にはLINEを活用、中年層にはFacebook、若年層にはInstagramなど。さらに、病院の特色に合わせた発信も重要です。例えば、スポーツをする若者向けに、整形外科の「スポーツ整形」の情報を発信する場合は、より若年層にリーチできる媒体を選ぶといった工夫が求められます。
また、広報誌をデジタルブック化することも可能です。すでに紙の広報誌を作っている病院でも、それをデジタル化して提供すれば、より多くの人に読んでもらうことができます。
今後は、紙媒体とデジタルをミックスし、適切な手段で情報を発信することが必要になってくると考えています。
ー NPO法人は設立から約25年、1991年には研究会としてスタートされたと伺っています。当時は「病院があれば人が来る」という考えが一般的でしたが、広報の重要性にいち早く注目されたのは先見の明があったと感じます。NPO法人設立のきっかけや、広報に着目された理由をお聞かせください。
実は、広報に本格的に取り組み始めたのは比較的最近で、約15年前くらいからですね。
それ以前は、NPO法人の紹介にもあるように、医療経営を支える事務職(アドミニストレーター)の役割について学ぶことが中心でした。勉強会を開催し、医療機関の運営を支える人材育成に力を入れていたんです。
広報に関して意識し始めたのは20年ほど前ですね。当時、アメリカで医療広告規制が緩和され、マーケティングの視点を含めた「医療広告」という考え方が広がっていました。その影響で、日本でも病院が「伝える」ことの重要性に注目されるようになりました。
私自身が所属していた別の研究会では、デザインとともに広報発信を始める動きがあり、それを学びながら、広報の研究会を立ち上げました。
この研究会も、毎年1回開催し続けて20回を迎えることになります。こうして少しずつ、病院広報の研究と実践を積み重ねてきたという流れですね。
ー 病院経営から広報へと発展し、広報こそが病院経営の質を高め、職員のやりがいや地域とのつながりを生み出す起点になると改めて感じました。広報の重要性をさらに多くの方に知っていただくためにも、NPO法人メディカルコンソーシアムネットワークグループのホームページをぜひご覧いただきたいと思います。本日は貴重なお話をありがとうございました!