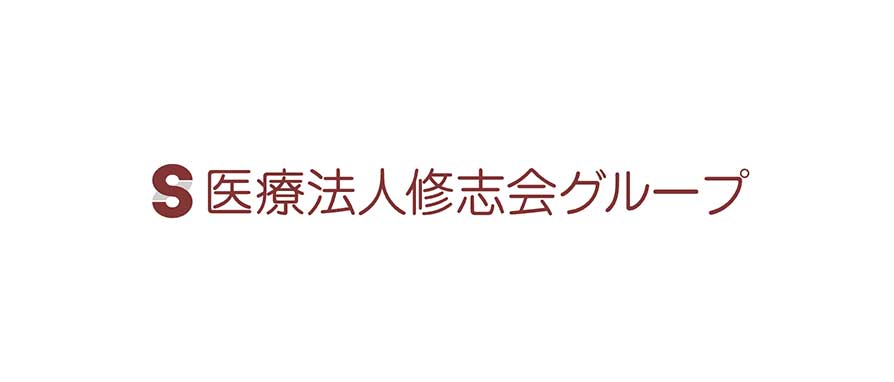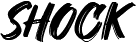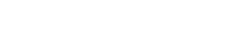
Radio Program

Delivering heartfelt, personalized healthcare.
心のこもったオーダーメイドの医療をお届けする
地方医療を変革するソーシャルイノベーターの挑戦に迫る
Special Guest:NISHIDA YUSUKE
スペシャルゲスト:西田 雄介さま / 医療法人修志会グループ 理事長
ー 本日は、医療福祉業界のイノベーティブな活動をなされている方をお招きしております。本日のゲストは、医療法人修志会グループ 理事長であられます西田雄介さんです。先生は2017年に埼玉県でご開業なされ、現在では東京・埼玉の他にも、神奈川、福岡にてクリニック、訪問看護ステーション、訪問マッサージを運営される医療法人修志会の若きリーダーとしてご活躍なされていると伺っております。西田先生のご出身は広島と伺っていますが、埼玉県越谷をクリニックの開業の地に選ばれた理由を教えていただけますか。
埼玉県は人口が多いにもかかわらず、病院の数が非常に少ない地域です。東京の隣に位置していますが、意外と知られておらず、医療が不足しているエリアでもあります。
そうした背景から、ニーズがあると考え、この地域での医療活動に取り組むことを決めました。
ー 修志会グループの特に素晴らしいと感じるのは、あえて過疎地域など医療が不足している地域に向けてサービスを展開し、医療を届けている点です。また、経営理念として「素晴らしい医療を届ける」という強い思いがあり、細やかな部分にまで目を向けながら活動されていると感じていますがいかがでしょうか。
私たちの理念は、「オーダーメイドの医療を届ける」ことですが、根本的な行動規範としては目の前で困っている人に手を差し伸べるというシンプルな思いで活動しています。
特に、医療サービスが届きにくい方々には、積極的に関心を持ち、事業を展開していきたいと考えています。
ー 先生はもともと外科医としてキャリアをスタートされたと伺っています。そこから整形外科を選ばれ、さらに現在は地域診療に取り組み、創業という新たなチャレンジをされています。なぜこの道を選び、地域医療に挑戦しようとされたのか、その経緯をお聞かせいただけますか?
最初は、純粋に手術をしたいという思いと、スポーツが好きだったことから、自然と整形外科を選びました。
その後、手術を終えて退院した患者さんが自宅でどのように過ごしているのかに関心を持つようになりました。また、父が広島の田舎で内科医として応診や訪問診療を行っていたことも、無意識のうちに影響を受けていたと思います。
そうした背景から、次第に訪問診療に興味を持ち、この道を選びました。
ー お父様の姿にも影響を受けていらっしゃるのではないかと思いますが、ご経歴を拝見すると、その途中でバックパックで世界を回られた経験もお持ちですよね。バックパッカーとして世界を回られた経験から、何か得られたことや、医療に対する考え方に影響を与えたことはありますでしょうか?
外科医として働いていた頃は、組織の一員として日々の業務をこなすことが中心で、自分で選択する機会が限られていました。
しかし、バックパッカーとして世界を旅する中で、多くの人との出会いがありました。彼らは「明日はどこへ行こう」「来月は何をしよう」と、すべて自分で考え、行動していました。その姿を見て、「これこそが人間らしい生き方だ」と強く感じました。
この経験を通じて、私も自分の道は自分で決めて生きていきたいと思うようになりました。
ー 往診クリニックなど西田理事長のもとで次々と開業が進み、規模が拡大していますが、その中で、開業における苦労や、人との関わり方、連携の面で特に重視されている点があれば、お聞かせいただけますか?
人を大切にすることを何より重視しています。
それは、患者さんを一人の人間として尊重することはもちろん、スタッフに対しても同じです。スタッフも、自らの意思で当院を選んでくれた大切な存在なので、しっかりと大切にしていきたいと思っています。

ー お仕事の中で大変なことも多いかと思いますが、往診をされる中で最も印象的だったエピソードや、特に現場力が試された場面などはありますでしょうか?
印象的なエピソードはたくさんありますが、特に大変だったのはコロナ第7波の時ですね。
当時は、コロナ診察や職員の体調管理のマニュアルもなく、すべてを一から作りながら診察を続ける状況でした。埼玉県東部では、当院が最も多くコロナ患者の往診を行ったと言われています。
発熱患者が行政に連絡すると、行政から「まずこのクリニックに電話してください」と当院を案内される形で、毎日多くの患者さんの対応に追われ、本当に大変でした。
ー 訪問診療や往診は、患者さん一人ひとりに合わせたオーダーメイドの医療を提供する上で、欠かせないものだと考えています。一方で、事業の継続に悩む医療機関も多いと聞いています。今後、訪問診療の需要がどのように変化していくのか、また、これから訪問診療のビジネスモデルを目指す方々に向けて、メッセージをいただけますでしょうか?
訪問診療はコロナの影響で都心部では少しずつ広まり、定着してきた印象があります。しかし、地方ではまだ十分に根付いていない部分も多く、私たちはそうした地域への展開を進めていきたいと考えています。
また、訪問診療は一つの医療機関だけではドクターの負担が大きくなりがちです。そのため、これから訪問診療を目指す若い先生方には、チームでの運営や他の医療機関との連携を意識することをおすすめします。それにより、より良い医療の提供が可能になると思います。
ー 西田理事長は、ドクターとしての側面だけでなく、経営者としての視点も持ち、さらに70~100人のドクターを束ねる立場でもあります。その中で、経営の課題や工夫している点、また今後の往診における報酬体系や収益モデルについて、どのようにお考えか、お聞かせいただけますでしょうか?
診療の収益に関しては、保険診療という限られた財源の中で成り立っているため、今後大きく収益が伸びていくかは疑問だと感じています。
しかし、その中でも質の高い医療を提供することがしっかり評価されていくことが重要だと考えています。
ー 今後、訪問診療や往診の分野では、マンパワーに頼るだけでなく、最新の医療技術やITツールの活用が求められていると思います。修志会グループとして取り入れようと考えていることや、先進的な取り組みについてお聞かせいただけますでしょうか?
そうですね。一昨年から、まず法人本部の強化に取り組んでいます。
クリニック単位で法人本部をしっかり整え、管理部門ごとに責任者を配置する体制は、まだあまり一般的ではないと思います。そこで、あえて医療従事者以外の幅広い人材を集め、情報システム部、総務、広報などの専門職を配置し、法人本部が機能することで現場を支えています。
この体制を整えることで、現場の医療従事者が診療に専念できる環境を作ることを目指しており、この点が他とは異なる取り組みだと考えています。
ー 特に人材確保は大きな課題だと思いますが、どのような工夫をされているのでしょうか?ドクターの採用や、適材適所の人材配置において、意識している点があればお聞かせください。
人材確保については、試行錯誤しながら取り組んでいるところです。
まず、「一緒に働くことで学べること」「チームでの環境の魅力」 を伝え、入職のメリットを感じてもらうことを意識しています。
また、ドクターの採用については、信頼できる方からの紹介 を重視し、地道に人のつながりを広げる形で進めています。いわゆる 芋づる式 で、信用のおける方同士をつなげながら採用を行っています。
ー 昨今、医療や介護のニーズはますます高まる一方、日本では介護・医療人材の不足が深刻化しています。海外からの人材受け入れや、日本で働く外国人への対応について、何か具体的な取り組みがあれば教えてください。
必要性は強く感じていますが、現状ではまだ具体的な動きはできていないのが正直なところです。
ただ、病院を見ても海外出身の看護師などが増えている印象があり、今後は私たちもそうした人材の受け入れについて少しずつ考えていく必要があると感じています。
ー 今後の展望として、修志会グループとして新たに取り組みたいサービスや事業があれば、お聞かせいただけますか?医療に限らず、他分野での構想や、西田理事長の思いが込められた取り組みなどがあれば、ぜひ教えてください。
現在、6つの成長戦略を掲げています。
一つ目は地方医療の活性化で、これは日本全体の大きな課題と捉えています。次に、大川さんの会社とも連携しながら精神科訪問診療や小児在宅医療を充実させることを考えています。また、訪問看護ステーションの強化も重要なテーマで、特に重症の患者さんを在宅で支えるためには、訪問看護の充実が欠かせません。
さらに、医療や介護の枠を超えた地域包括ケアシステムの構築を目指しています。これは単にクリニックや医療機関を整備するのではなく、町全体で高齢者や社会的弱者を支えていく仕組みを作るという考え方です。少し規模の大きな話にはなりますが、そうした地域づくりにも貢献していきたいと思っています。
また、医療DXの推進にも取り組んでおり、デジタル技術を活用して医療の効率化を進めています。最後に、今後の医療を支えるためには後継者問題の解決も重要です。事業承継に悩むクリニックをサポートし、医療サービスを継続できるような仕組みを作ることも考えています。
ー 最近話題に上がったニセコのケースのように、十分なインフラが整っていない地域も少なくありません。また、終末期医療に関する相談は特に多いと思いますが、どのように対応し、向き合っているのか、お聞かせいただけますでしょうか?
終末期医療については、確かに在宅でできる医療行為がこの10年で大幅に増え、相談が非常に多くなっています。また、以前は「病院で最期を迎えるのが当たり前」という考え方が主流でしたが、「住み慣れた自宅で最期を迎えたい」という患者さんの意識も大きく変わってきたと感じます。
そのため、依頼も増えており、私たちは適切な医療を提供するだけでなく、患者さんが後悔のない最期を迎えられるようなアドバイスをすることを大切にしています。スタッフにも、常にその意識を持って対応するよう伝えています。

ー また、都市部と地方ではクリニックの運営方針や課題が大きく異なると思いますが、他のクリニックとの差別化を図るために西田理事長が取り組んでいることがあれば、可能な範囲で教えていただけますでしょうか?
街づくりの観点では、訪問診療の開業からスタートしましたが、困っている人に手を差し伸べるために、不足しているサービスを法人内でどんどん増やしていきたいという考えで取り組んでいます。
その一つが外来クリニックの設立です。もともと外来に通院していた患者さんが、スムーズに在宅医療へ移行できるような仕組みを整えています。
また、大川さんの会社と提携し、クリニックの隣にカフェを併設することで、医療をより身近に感じてもらえるような環境づくりにも取り組んでいます。さらに、お祭りに参加するなど、地域住民とのコミュニケーションを深める活動も積極的に行っています。
ー 続いて医療のテクノロジーとデジタル化についてお聞きしたいと思います。訪問診療におけるAI診断、電子カルテ、遠隔モニタリング、オンライン診療など、医療DXの活用が進んでいますが、今後「まだ導入はしていないが、患者さんのためになりそうな技術やサービス」について、何か考えられることはありますか?
私自身はITが得意ではないので、社内の担当者と相談しながら進めていますが、訪問診療の観点ではより多くの患者さんを効率的に診るためのルート最適化技術が有益だと考えています。最近では、そうした技術を提供する企業も増えており、コラボレーションすることで互いにメリットがあるのではないかと思います。
また、医療機関自体がIT導入の遅れている分野だと感じています。そのため、社内の業務効率化を目的にアプリ導入なども試みていますが、技術が優れていても、使用者のITリテラシーによって浸透が難しいという課題もあります。
その点で、国が進めているリスキリング(学び直し)の取り組みは、今後の医療業界にとって非常に重要になると感じています。
ー 素朴な疑問なのですが、なぜ修志会グループはこうした取り組みが実現できているのでしょうか?2017年に創業されてからまだ若い医療法人でありながら、地域医療の充実に取り組み、オーダーメイド医療を提供し続けています。どのようにしてこの体制を築き上げ、維持できているのか、改めてお聞かせいただけますか?
そうですね。やはり「人を大切にすること」を大前提にしているのが大きいと思います。
核となるドクターやバックヤードのスタッフがいて、さらにその人たちが新たな人材を連れてきてくれる。そうした人のつながりを大事にする組織だからこそ、成長を続けられているのだと感じています。
今後も、その理念に共感してくれる人が増えれば、さらにできることが広がっていくのではないかと思っています。
ー オーダーメイド医療というと、多くの方にはまだ馴染みがないかもしれません。しかし、先ほど「人を大切にする」というお話がありましたが、そうした考え方の中で本当にオーダーメイド医療を実現することは可能なのでしょうか?
病院で外科医をしていた頃は、なかなか実現できなかったかもしれませんが、在宅医療では一人ひとりの患者さんとしっかり向き合う時間を確保できることが大きな違いです。
患者さんが何を望み、何を望まないのかを丁寧に聞き取り、適切な医療知識のもとで、その希望に沿った治療やサービスを提供することを大切にしています。
ー 医療や福祉の未来にはさまざまな課題もありますが、こうしたリーダーが地域で活躍されていることに、希望を感じた方も多いのではないでしょうか。修志会グループの活動をこれからも応援させていただきたいと思います。本日はありがとうございました!