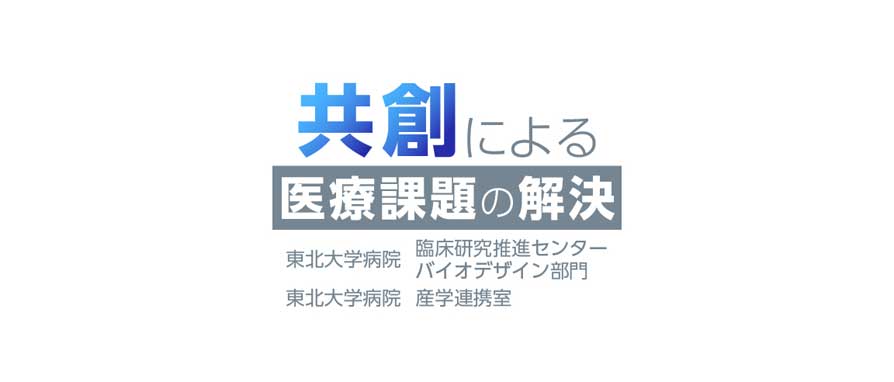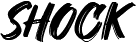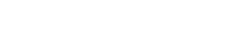
Radio Program

The Frontlines of Medical Innovation.
医療イノベーション最前線
東北大学病院の挑戦!デザイン思考と産学連携の力とは
Special Guest:NAKAGAWA ATSUHIRO
スペシャルゲスト:中川 敦寛さま / 東北大学病院 教授、 産学連携室 デザインヘッド
ー 本日は、NECと東北大学病院が、第7回日本オープンイノベーション大賞において日本学術会議会長賞を受賞されたというリリースから、このオープンイノベーションと、大学病院とのコラボレーションが社会実装にどのように貢献しているのかについて、ぜひお話を伺いたいと思います。お話を伺いますのは、東北大学病院教授であり、産学連携室デザインヘッドでもある中川敦寛先生です。産学連携室というのは、大学病院内に存在し、さまざまな取り組みを東北大学病院で行っていると伺っております。その旗振り役の一人が中川先生だとお聞きしました。
これまで、病院というと病気になって診断を受け、治療を行うというのが一般的なイメージであり、今もそのような形が多いと思います。しかし、これからの日本は非常に多くの課題を抱える国になっていきます。例えば、先日も上水道や下水道の問題が取り上げられましたが、具体的な数字を挙げると、2015年には15歳から65歳の人口が7100万人程度でしたが、2060年には6000万人に減少し、2200年には3900万人になるという予測があります。
その一方で、東北地方を見渡すと、私の出身地である長野県をはじめ、秋田県のように65歳以上の高齢者人口が40%に達しようという地域もあります。つまり、税収は減り、働き手が減少していく中で、やらなければならないことがどんどん増えていくという大きなミスマッチの時代に、2060年頃まで私たちは生きていかなければなりません。
このような状況に対して、現在、東北大学では、前病院長の冨永先生や現病院長の張替先生のもと、病院が果たすべき新たな役割を模索しています。自分たちだけで行動してもインパクトを出すのは難しいため、企業の方々と共に共創、コークリエーションを行っているのです。社会課題を解決するためには、手弁当で無限の労力をかけるだけでは持続可能ではありません。
そこで、社会課題を解決しつつ、経済規模のあるビジネスを作り上げることが重要です。これにより、解決策をどんどん広げ、少ない労力で大きなインパクトを生み出せるような仕事の仕方を提供し、社会課題を解決しながらビジネスを創出していきたいと考えています。最終的には、もっと大きなことを成し遂げる場所として、病院を活用していこうとしています。
ー 今回の冒頭でご紹介したのは、NECさんとの共同研究と、この賞を受賞されたことについてですが、NECさんは関わっている法人の一社として考えればよいですね。
先ほどお話ししたように、多くの企業さんと補完的な関係を築いており、英語では「コンプリメンタリー」と表現されますが、その関係を通じてインパクトを生み出しています。フェイスワークで高いインパクトを出し、全体デザインを担うことで、新たなビジネス的価値を創出したいと考えています。
私自身の年間の業務では、100社を超える企業への戦略コンサルティングからスタートアップ支援まで行っています。スタートアップ支援に関しては、現状では主に海外のアドバイザーのみが担当しており、毎年約10%の案件を海外で担当しています。NEC様とは長い付き合いがあり、100社を超える中の重要なパートナーとして、長期間お付き合いさせていただいております。
ー こうした取り組みは、一朝一夕にできるものではありません。東北大学病院の歴史の中で紹介したいプログラムがあります。それが「ベッドサイドソリューションプログラム」、通称アカデミックサイエンスユニット(ASU)です。このプログラムは、医療現場を開放し、多くの方々に関与してもらうことを目的としています。医療現場を開放することが良いことなのかという点についても議論があります。
まず、私はカリフォルニア大学サンフランシスコ校で基礎研究を臨床に持ち込み、さらにその臨床から社会へインパクトを与え、コミュニティを良くするという橋渡しのトレーニングを受けました。頭部外傷のフェローシップとして2008年から2010年までカリフォルニア大学サンフランシスコ校に在籍していました。その後、日本に戻り、大学で臨床特区の研究を進める中で、どのようにインパクトを出すかを考えていました。
その当時、若手の研究者たちと共にさまざまなプロトタイプやコンセプトを試し、実証を提供したりニーズを探索したりしていました。しかし、結論として言えるのは、日本には素晴らしい技術やタレントがあるものの、事業を監視するための課題にアクセスできていないケースが非常に多かったということです。億単位の損失が続出し、医療現場では、5分で解決できるはずの問題に何年も何億もかけて取り組んでいた案件がいくつもありました。
一方で、医療現場は患者さんやそのご家族、医療従事者が命をかけて戦っている場所でもあります。そのため、心配をかけたり支障をきたしたりすることは避けなければなりません。問題が発生した際には、適切な説明責任を果たせるようにする必要がありました。2010年から3年かけて制度設計を進め、医療現場を事業家に向けた場に変えるアイデアを実現しようとしました。
その結果、2014年3月31日には医療現場を開放するプログラム、ASU(アカデミックサイエンスユニット)が開始されました。当時は実証に向けて十分な人的リソースがなかったため、現場観察を行うプログラムとしてスタートしましたが、病院全体を開放する形で、適切な制度設計を行い、問題が発生した際には説明責任を果たせるようにしました。このプログラムの準備には3年近くの時間がかかりましたが、最終的にASUはそのような形で実現しました。
ー 約10年間にわたり、ベッドサイドソリューションプログラムに関しては、69社、1700名以上の方々が6ヶ月のプログラムに参加したと伺っています。一般的に、事業会社にはさまざまなアイデアや思いがあり、それらを病院の皆さんに活用してもらいたい、またはソーシャルなインパクトを生み出したいと考えています。しかし、その実現においてコミュニケーション不足が原因でうまくいっていなかったのではないかという点が挙げられます。
そうですね。まず、医療現場において企業の方が入ることは、当時は反対の声が強かったことがありました。制度設計を行った際、医療現場に企業が関わることは、どちらかというと逆風が強かったのです。しかし、だからといって、実際にお金を払う際には、やはりその価値が直接的に感じられなければ、支払いが発生しません。その価値を提供する現場を見ずに、どのようにしてお金を払ってもらえる設計ができるかという問題もありました。ですから、できないという理由ではなく、どうやって対立する要素をうまく調整し、実現していくかが我々デザイナーの役割だと思います。今振り返ると、そのために法律家や情報管理の専門家など、さまざまな方々に相談しながら進めました。
ー 今回、冒頭で中川先生の肩書として「デザインヘッド」という言葉があり、また先生の言葉の中にも「デザイナー」という表現がありました。特に医療現場では、先ほど触れたカリフォルニア大学やスタンフォード大学のデザイン思考が多くの方々に知られています。先生ご自身が考える「デザインヘッド」や「デザイン思考」とは、どのように定義し、学んでいけば良いのでしょうか。
デザインというのは、形状のデザインだけではなく、実際には「段取り」や「プロセス」のデザインを指します。私がデザインを学び始めたのは、スタンフォード大学の池野先生の導きで、2014年からスタンフォードのグローバルパーカルティトレーニングプログラムで勉強させていただきました。このプログラムでは、まず解決すべき課題を合理的かつ創造的にスクリーニングし、その中から解決に値する課題を選び、次にその課題に対してコンセプトを出し、それを発散させてから収束させるというプロセスを学びました。これがデザイン思考という考え方です。
「デザインヘッド」とは、デザインが企業やクライアントごとに異なる解決すべき課題を持ち、その課題が言語化されていないことも多いことを踏まえて、解決策を見出す役割を担うことを指します。私たちは「本質を聞き、本質をエレガントに一撃で解決する」ことを目指して、できるだけ「More Work, Less Impact」でなく、「Less Work, High Impact」を実現するようなデザインを提供しています。
そのためには、医療の知識だけでは不十分で、ビジネスやテクノロジー、デザイン、ヘルスケアなど、さまざまな分野に精通することが求められます。これを実現するために、私たちは国内外からインターンを受け入れ、これら4つの分野で一定の知識を持つことを重要視しています。デザインヘッドとは、こうした知識を活かしながら、全体デザインを行い、「Less Work, High Impact」を実現するプロセスをデザインする人を指します。

ー 先生は病院関連のセミナーで、ビジネスで大成功されている方々をゲストとして招いていらっしゃいます。こうした取り組みこそ、先生が語るデザイン思考が具体的に実装されている一例となるのでしょうか。
社会的課題を解決し、かつ経済的な規模も持つような事業をスタートさせる場として、病院を再定義することが、このプログラムの本質となります。これを実現するためには、まず課題設定が重要です。例えば、サンフランシスコで一番高いビルを建てた方と間接的に仕事をしていた際、その方から「東北地方独特の課題ではなく、人類全体の課題を解決するような問題を持ってきてほしい」と言われたことがあります。私は、その時に人類規模の課題でないと解決は難しいということを実感しました。
また、その方は「解決策を持ってきてください」とは言いませんでした。むしろ「東北地方独特の課題で解決に値するものを持ってきてください」と言われたのです。つまり、課題設定においてスケーラビリティを求めるなら、人類規模の問題である必要があるということです。
この観点から、東北大学のようなアカデミア病院を捉え直すと、世界中のアカデミアと素晴らしい方々、ノウハウ、そしてインフラと繋がることができます。課題を設定した後、その解決に必要なインフラ、エキスパート、ノウハウを組み合わせて最適化することが求められます。そして、世界で最も優れた専門家と協力すれば、その問題はエレガントに、かつ効率的に解決できるわけです。
こうした背景において、アカデミアだからこそ時間を割いてくださる方々にコミットしていただき、講演なども行っています。これにより、素晴らしい成果を成し遂げた方々と共に進めていくことができるのです。
ー 冒頭でご紹介した通り、第7回日本オープンイノベーション大賞をNECさんと共に受賞したことについてお話しします。この受賞内容は、「医療現場の革新と医師の働き方改革を目指す医療大規模言語モデルの研究開発と実用化」です。これにより、医療従事者の働き方改革が進んでおり、すでに実証もされています。先生が提唱されている病院の新しい定義や課題設定、デザイン思考がどのように実装されているのか、具体的な内容についてお伺いしたいと思います。
解決すべき最初の課題は医療現場の働き方改革です。医療現場も他の業界と同様に、多忙な状況で成り立ってきました。特に、海外で働く場合は、忙しい時期(オン)と休む時間(オフ)がしっかり分かれています。しかし、日本の医療現場では、使命感だけで多くの医師が働いており、この状況が持続可能でないことが問題視されています。2024年から法的な規制も強化されたことは、皆さんもご承知の通りです。
この状況において、医療現場の質を保ちながら、生産性をどのように向上させるかが課題となります。こうした課題に対応するため、2021年末にNECから世界レベルの技術を活用し、医療現場の課題を解決する提案がありました。
例えば、現在世界中の空港で使用されている顔認証技術は、NECの技術です。また、大規模言語モデルや音声認証技術も、世界レベルの技術を活用しています。これらの技術を用いて、2024年までに医療現場の課題を解決し製品化を目指したい、そんな大きなプロジェクトとして、2021年12月にお話をいただきました。
私たちはまず、大規模言語モデルを活用して、医療現場で解決可能な課題を30以上NECの皆様とともにリストアップしました。その中で、インパクトが大きく、かつハードルが低い課題を選定し、評価しました。その結果、インパクトが高く、ハードルが低い課題がいくつか残ることになります。
その中で最初に取り組んだのが、大規模言語モデルを用いて解決できる医療現場の課題です。例えば、20年間通院されている患者さんのカルテを、内科の先生が30分かけて確認し、その後外来に臨む場面がよくあります。この課題は、NECのテクノロジーを活用することで、インパクトが大きく、かつハードルが低いと考えました。その後、2番目、3番目の課題は、少しハードルが高いものの、インパクトも大きいと予測されました。このアプローチは「ドミノ効果」と呼べるもので、まず最初に簡単に解決できる課題(クイックウィン)を取り組むことで、勢いをつけ、その後の課題にも対応できるようにしていきます。
次に取り組んだ2つ目、3つ目の課題も、できるだけ簡単に解決できるようにデザインしました。そうすることで、勢いがついていきます。これをテクニカルタームで「モーメンタム」と言います。モーメンタムができると、後は自動的に、ドミノが倒れるように次々と進んでいきます。最初は批判的だった人たちも、次第に納得していくのです。これを実現するのがデザイナーとしての楽しみです。要するに、少ない労力で大きなインパクトを生み出すドミノ効果を作るのが私たちの仕事です。NECの技術を使ったドミノ効果が実現したので、今年の2月にはすでに3件のプレスリリースが発表されました。
例えば、放射線科の先生が作成したレポートから、がんの分類が推定でき、これがコンテストで賞を取ったり、知見に繋がったりしています。現在、日本では最先端の薬剤がなかなか国内に入ってこないという問題があります。ドラッグラグやロスといった課題は社会問題となっており、特に珍しい疾患の患者さんを対象にした知見では、的確な患者さんを見つけるのに時間がかかりすぎるという問題があります。その結果、試験を実施するには多大なコストがかかり、1日あたりの予算だけでも非常に高額になっています。このような問題にも取り組んでいます。
LLMを使うことで、より短い時間でより多くの患者さんを的確な基準で探し出せるようになり、これについても3月6日にプレスリリースが発表されました。これが2つ目、3つ目の成果として並んでいます。このようなドミノ効果を生み出すために、2023年12月には耳鼻咽喉科の全面的な協力を得て、香取幸夫教授や石井講師をはじめとした耳鼻科の皆様に支援いただきました。その結果、概念実証が進み、2024年3月にはNECさんから製品化が発表されました。このプロセスを通じて、私たちは現場での貢献や医療従事者へのインタビューだけでなく、レスワーク、ハイインパクトを実現するためのドミノ効果を作り出すことに貢献したと考えています。この点が評価されているのではないかと思います。

ー AI技術は日々進化していますが、今後さらに多くの医療従事者や医療機関に普及させるためには、制度改革や現場での教育が重要な課題となります。これらの課題について、先生からお聞かせいただけますでしょうか。
解決しなければならない課題は多くありますが、まず制度面について言うと、過度な課題もあるかもしれません。日本は間違いなく今後、課題先進国としてチャンスがあるとも言われています。しかし、これまで多国籍企業のCXOや役員の方々とお仕事をしてきた経験から、課題がエレガントに解決できない場合、逆に課題先進国になるという危機感も感じています。
そのため、まずは危機感を持ち、外に出て日本を外から眺めることが重要です。その中で、どのように自分が貢献できるかを考えるチャンスを、若い世代にもっと提供することが大切だと思っています。東北大学も、「国際卓越研究大学」に指定され、これから25年間にわたり様々なチャレンジを冨永総長のもとで行っていく予定です。
その中で、若い世代の方々が外に出て、日本をどう見て、どのように自分が貢献できるかを考える機会を作ることが、私たちの責務だと考えています。また、若い世代を支援するためのプログラムを作り続けることが重要です。
私たちのところにはアルバイトの学生が数十名いますが、上司からよく言われるのは、「自分の一番大事な仕事は、彼らの邪魔をしないこと」だということです。なぜ自分がやっている仕事が重要なのか、その意義を時間をかけて説明しています。特に今のZ世代は、意義を感じると、自分たちが考えもしなかったような行動をする場面をよく目にします。大谷さんのような例がその代表です。
これからは、若い方々の可能性を広げるきっかけを作ることが重要です。今の常識ではできないということを言わずに、上手にサポートできるよう、自分自身も変わり続けていきたいと考えています。
ー 先生ご自身の今後5年後、10年後のビジョンについてお聞きしたいと思います。これから医師として、またデザインヘッドなどのリーダーとしてどのように活動を展開されていくのか、メッセージもお聞かせいただけますでしょうか。
リーダーシップについて、私はジェフリー・マンリー先生から学んだことがあります。彼が示していたリーダーシップは、いわゆるサーバントリーダーシップで、英語でいう「ノーススター」、つまり北極星のように、どこに向かって進むべきか、みんなでその目標に向かって進もうという考え方です。しかし、旅が始まった後は、その旅路を共に歩んでくれる人々が直面する困難を、私は後ろからサポートする役割だと考えています。ジェフのリーダーシップを見てきて、私はこのような形でリーダーシップを発揮していきたいと思っています。
もちろん、自分が夢を持ち、その夢を一緒に見てくれる仲間をサポートできる力をつけていきたいという強い思いがあります。今後、私たちが迎えるのは、大きなミスマッチの時代です。日本の市場は縮小し、より多くの課題に直面するでしょう。だからこそ、私は日本から世界に向けて発信し、経済的な規模を持つような事業を展開し、世界に貢献していきたいと考えています。これを実現するためには、免許を持つような確かな能力を証明し、さらにグローバルに広がる課題を解決していくことが求められると感じています。
また、私たちはこれから「国際卓越研究大学」という新しいチャンスを得て、これを活かして新しいアカデミアの価値を国際的なネットワークを通じて発信していこうとしています。もちろん、試練も多くありますが、こうした取り組みを通じて、日本がもっと豊かで幸せな国になり、日本人が誇りを持てるような社会を作り上げていきたいと思っています。そのために、アカデミアや医師免許を持つ私たちができる限りの貢献をしていくことが、最終的には大きな成果に繋がると信じています。
ー 先生の内に秘めたエネルギーとお人柄に触れることができ、大変貴重な時間となりました。これからの東北大学病院の素晴らしい活動を、私たちも発信していきたいと思っています。本日はありがとうございました!