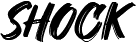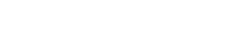
Radio Program

Sales Revenue Tripled in the Last 10 Years!?
過去10年間で売上高を3倍以上!?
医療の質向上と経営の安定化に必要な優秀な医師の採用をなぜ実現できるのか
Special Guest:MAEDA MASAAKI
スペシャルゲスト:前田 昌亮さま / 社会医療法人杏嶺会 一宮西病院 事務長
ー 本日は医療業界のイノベーションについてお話を伺って参ります。本日のゲストは社会医療法人杏嶺会 一宮西病院 事務長の前田 昌亮さんです。一宮西病院は、週間東洋経済の特集「都市部でも病院が消える時代 病院大淘汰」で、なんと売上高は10年で3倍を超えるという取り組みを紹介されていました。
一宮西病院は2001年に開院し、約20年以上にわたり地域医療を支えてきました。2023年には増床を行い、がん診療や在宅医療にも力を入れています。現在、一般病棟587床、回復期リハビリテーション180床を有し、37の診療科を持つ大きな病院です。直近ではコロナ禍や移転がありましたが、業績は回復し、2024年度には売上高350億円、営業利益35億円を見込んでいます。また社会医療法人として認可を受けた法人であり、その規模と実績は注目されています。このような運営が可能な理由を教えていただけますか?
秘密にしているわけではありませんが、当院の特徴はやはりドクターにあると私は考えています。東洋経済の記事でも触れられている通り、まず私たちの病院では、過去10年間でドクターの数が大きく増加しました。平成26年時点で約60名だった常勤ドクターが、令和6年の4月時点で219名にまで増えています。
その理由として、私たちの病院の歴史背景も関係しています。一般的な病院は大学医局から派遣される医師に頼って医師を確保するのが一般的ですが、当院ではその方式に頼らず、自前で医師を採用してきたことが特徴です。
つまり、地域に必要な医療を考え、それに適したドクターを全国から探し、医師とのご縁を作り出してきた結果、今の医師数に繋がっています。このアプローチが、地域医療で実際に提供したい医療を可能にし、患者様や利用者様が当院を支持してくださる理由となっているのだと思います。その結果として、売上などの数字にも結びついているのだと思います。
ー 医師の採用について、年間25~30人を採用し、1人を採用するために30人にアプローチするということですので、年間で750~900人の医師に接触している計算になります。もちろん医師は多く存在しますが、これを企画されたのが前田さんということになりますでしょうか。
はい、私が前職でヘッドハンティング会社にいた経験を活かし、スカウト理論をこの病院に導入しました。現在、当院には人事部門があり、ドクター専門の採用チームがあります。このチームは、研修医を対象にするグループ、後期選考を行うグループ、そして中堅や部長クラスのドクターを対象にするグループの3つに分かれています。それぞれのグループには、全国で活躍している8人のメンバーがいます。私が伝えたスカウト方法を実践し、厳しいプロセス管理のもとでドクターとの交渉を行っているという状況です。一人でできる数字ではないため、しっかりとマネジメントしています。

ー 全国の医療機関の皆さんがその秘密を知りたがっていると思いますので、公開できる範囲でお話しいただけますか。
私たちの病院がある一宮市は、3つの総合病院があり、十分な医療が提供されていると思われがちですが、例えば肝臓専門医が不足しているという問題があります。肝臓の専門医がいないため、重大な肝臓疾患にかかった場合、患者さんは他の医療機関へ転院する必要があります。そこで、肝臓専門医を探すことが重要となり、インターネットを活用して、医師の情報を集める方法を取りました。
病院のホームページや学会のサイトで専門医の情報を得ることができ、さらに厚生労働省のサイトでは医師の免許取得年もわかります。この情報を基に、私たちは肝臓専門医のリストを作成し、スカウト活動に進みます。私の経験を活かして、スカウトレターを直筆で書き、医師に送ることで、興味を示していただいた方々と面会し、相思相愛の関係を築くことを目指します。
さらに、医師の評判を確認し、実際に優れた評判を得ている医師だけにお手紙を送るという方法を採っています。こうした手法で、確率的に良い結果を得ることができており、これは私たちが取り組んでいる秘密の一つです。
ー 病院の「断らない医療」という理念のもと、専門医がいない分野でも他の専門医と連携し、地域のニーズに応じた医療を提供する姿勢が強調されています。街と人が明るく健康に暮らせるように、その思いを実践することが重要だということですね。
多くの病院が「断らない医療」を掲げていると思いますが、実際には病院で対応できない医療があれば断らざるを得ませんし、患者さんを受け入れても正しい医療を提供できないこともあります。そのため、私たちの病院では、小児科医が365日24時間常に病院内にいて、小児救急を必ず受け入れられる体制を整えています。これは「断らない医療」の理念を実践するために必要な取り組みです。
また、もう一つ重要な取り組みはベッドコントロールです。病床がいっぱいで入院を受け入れられない状況が発生することがありますが、これが起こる原因の一つはベッドコントロールがうまく機能していないことです。私たちの病院では、事務部門がベッドコントロールを主導しており、ドクターや看護師、ケースワーカーが協力して業務を進めています。この体制が私たちの病院の特徴の一つだと思います。

ー 前田さんはヘッドハンティングのキャリアを持ち、さらにキーエンスでの勤務経験もあります。なぜこのような異なる体制が一宮西病院で実現されているのでしょうか。また、前田さんがなぜこの病院を選び、キャリアを大きくチェンジしたのか、その判断の理由についてお伺いしてもよろしいでしょうか。
私の経歴については、新卒でキーエンスに入社し、5年間働きました。最初にキーエンスを選んだ理由は、家族が経済的に苦しく、母親を楽にさせたかったからです。その後、働きたかった会社であるパーソルキャリア(当時の社名はインテリジェンス)に転職し、さらに5年間人材紹介業務を経験しました。
その中で感じたのは、転職マッチングが無理に感じることも多かったということです。特にリーマンショックの時期で、社会的価値に疑問を感じるようになりました。ヘッドハンティング業界に移り、必要な人材を見つける仕事はとても満足感があり、ウィンウィンの関係が築けると実感しました。しかし、さまざまな業界を扱う難しさも感じ、最終的には一つの業界で自分の力を活かしたいという思いが強くなり、縁があって一宮西病院に入ることになりました。
医療業界に入って驚いたのは、ドクターのヒエラルキーの高さです。しかし、彼らは純粋に患者を治す技術者であり、私はそのサポートをするべきだと感じました。医師と対等に話せる立場だったので、問題を解決するために積極的に意見を交わすことができました。私がドクターを自分で採用し、直接コミュニケーションを取ることで、フラットな関係が築け、事務長としてもスムーズに業務を進めることができました。この経験が、一宮西病院の独特な運営方法につながっています。
ー 現在、赤字経営の病院が増え、破綻するケースも目立っています。この問題をどう見ているか、またどのように改善できるかについてアドバイスをいただければと思います。どのような対策を講じれば、不安が解消されるのでしょうか。
私は、不安を感じる理由は病院の事務部門が十分に強化されていないことにあると思います。病院の運営は、事務部門の強化にかかっていると言っても過言ではありません。医療業界全体として、文系職種の人材をどのように採用するかが重要だと思います。現在、大学を卒業した多くの若者は総合商社や金融機関に就職していますが、私は将来的に医療法人がその選択肢の一つとして挙がることを望んでいます。病院の事務職が経営を考え、医師や看護師をサポートし、地域医療に柔軟に対応することが最も重要です。
現状、病院の運営は病院長、事務長、看護部長の3人で任されていることが多いですが、これはなかなか進展しないことが多いです。医療技術者はそれぞれの分野に特化しているため、協力して同じ方向に進むのは難しいのです。そのため、事務部門が間に入って指導し、方向性を示すことが必要です。しかし、現在の組織にはそのような人材が不足していることが多いと思います。そうした人材は転職市場や大学で見つけることができるので、病院がその人材をどのように取り込むかが、今後のスタートラインだと考えています。
ー 現状はまだプロセスの途中ですが、今後の一ノ宮西病院の運営について、事務長としてどのように進めていくか、メッセージをいただけますか。
当院はまだ実現できていない医療やサービスがあり、また受け入れていない患者様もいます。職員の就業環境に満足していない面もあると感じていますが、最も大切なのは病院が成長し続け、事業を拡大していくことだと思っています。そのために、足りない医療やサービスを見つけ出し、それを実現することで職員の増員が進み、新しい価値を提供していると実感できることが職員の誇りに繋がると信じています。今後はこの方向で邁進し、進めていきたいと考えています。
ー 地域医療における一宮西病院の取り組みと成長を深く知ることができました。今後もこの取り組みがさらに発展していくことを期待しています。本日はありがとうございました。