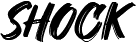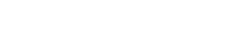
Radio Program

Redefining Social Norms
社会の常識を変えていく
誰もが対等に働ける未来──IT特化型特例子会社「日揮パラレルテクノロジーズ」の挑戦
Special Guest:AWATARI KENTA
スペシャルゲスト:阿渡 健太さま / 日揮パラレルテクノロジーズ 株式会社 代表取締役社長
ー 本日のゲストはプラントエンジニアリングの分野で世界的に知られる大企業"日揮"のグループ会社として設立された日揮パラレルテクノロジーズ株式会社 代表取締役社長の阿渡健太さんです。改めて「日揮パラレルテクノロジーズ株式会社」とは、どのような仕事をされている会社なのか教えていただけますか。
弊社は、日揮グループの中でもITやDX(デジタルトランスフォーメーション)に特化した業務を担っています。日揮グループの各社から、業務のIT化・DX化の依頼を受け、それを弊社のITエンジニアたちが技術で形にする。そして、グループ内やその先のお客様に向けて納品しています。一言で言うと、「IT系の仕事」をしています。
ー 阿渡さんは、前代表と共にこの会社を2021年に設立され、コロナ禍の中で活動をスタートされました。そして副社長を経て、昨年3月から代表取締役に就任されたんですね。御社で働いている多くの方が障害をお持ちだと伺いました。阿渡さんご自身も、障害をお持ちだそうですね。
そうですね。私は生まれつき身体に障害がありまして、両腕がありません。ラジオでは伝わりにくいかもしれませんが、両手ともない状態で生まれてきました。
ー 阿渡さんはご自身の障害と向き合いながら、パラアスリートとして活躍する一方で、YouTubeなどを通じて日常生活の工夫を発信し、多くの人に気づきや勇気を届けてきました。冒頭から質問攻めになってしまいますが、設立の経緯や障害者雇用の現状などを教えていただけますでしょうか。
会社が設立されたのは2021年です。ですが、その2年前の2019年に日揮という会社が、事業再編のために3社に分社化されたんですね。その結果、それまで1つの会社にまとまっていた障害者の雇用が3社に分散してしまった。結果的に、そのうちの1社で障害者の雇用率が基準を下回ってしまい、行政から是正を求められました。
当時、私は日揮本社で採用担当をしていたのですが、その課題にどう対応するか、1年かけて検討を重ねました。さまざまな方法がある中で、最終的に「特例子会社」を設立することに決めたんです。これは、特例子会社を通じてグループ全体で障害者雇用を通算できるという制度を活用することで、グループ全体の雇用率を安定させる仕組みです。そうして、2021年1月に日揮パラレルテクノロジーズが設立されました。
ー 特例子会社については、法定雇用率の達成を目的に、赤字覚悟で運営されるケースも少なくないと聞きます。本業と関係の薄い農業などを行っている例もあり、障害者雇用に対してネガティブな印象を持つ方もいるかもしれませんが御社の取り組みは、そうしたイメージを覆すものですよね。
そうですね。あとで詳しくお話しできればと思いますが、私たちは他の企業にはない「働き方の制度」を導入していて、それがとてもうまく機能しています。特に、就労が難しいとされてきた精神・発達障害のある方々が、安定して働き続けられる環境をつくれていると思っています。

ー 御社は、IT戦略と人材雇用を両立させる企業として注目されています。なかでも「フルリモート・フルフレックス」という働き方は大きな特徴です。導入の経緯や、そのメリットについて教えてください。
特例子会社を立ち上げると決まった際、まず考えたのが「どんな事業をやるか」ということでした。いろいろな特例子会社を見学したのですが、そこでよく見られたのは、コピーやシュレッダー、メール便の仕分けなど、いわゆる軽作業でした。もちろんそうした仕事が悪いというわけではありませんが、「誰でもできる」「やがて機械に置き換わる」ものばかりで、やりがいや将来性に疑問を感じました。
そんな中、とあるIT系の就労移行支援事業所を見学した際、非常にスキルの高い障害者の方々と出会いました。彼らはIT技術に優れていたのですが、障害の特性ゆえに、一般的な企業では働くのが難しい状況にありました。それならば、働く上での「ハードル」をこちらが極力取り除けば、彼らが自分の力を発揮できる環境がつくれるのではないか。そう考えて導入したのが、「フルリモート・フルフレックス」という働き方です。
ー フルリモートとフルフレックスによって、働く上でのハードルを下げ、多くの人の可能性を引き出せる。その一方で、制度をつくることと、それを機能させ続けることは別物だと思います。実際に制度を回すうえで、どのように組織づくりをされているのでしょうか?
結論から言うと、今のところ非常にうまくいっています。フルリモートなので、本社は横浜にありますが、社員は全国各地に点在しています。普段の業務は、こうしてオンラインで行っています。
精神・発達障害のある方が多いのですが、彼らが抱える困難の多くは、出勤そのものにあります。たとえば、満員電車に乗ることができない、オフィスの光や匂いで集中できない、雑談が苦手など、さまざまです。ですが、フルリモートによって、これらの負担を一気に解消することができます。自宅で働くことで、自分に合った光の量、匂い、椅子や机の高さなど、すべてを自分仕様にできる。これが非常に大きなメリットです。
また、フルフレックスの制度も導入しています。人によって集中しやすい時間帯は異なります。朝型の人もいれば、夜型の人もいる。ですから「9時から18時まで働くべき」という考え方ではなく、自分が最もパフォーマンスを発揮できる時間帯を、自分で設計してもらっています。
ー 企業として利益も求められるなかで、御社では「ノーワーク・ノーペイ(働かざる者、報われず)」という考え方を導入されていますね。この制度の背景や意図について、改めて教えてください。
当然、働いた分だけ給与が支払われますので、週20時間で働けばその分の給与になります。これが「ノーワーク・ノーペイ」の考え方です。
大企業では、病気などで休職した場合にも一定期間給与が支払われるという制度がありますが、精神・発達障害のある方の雇用においては、こうした“手厚すぎる保障”がリスクと捉えられるケースもあります。だからこそ、私たちは最初から「働いた分だけ報われる」仕組みを明確にして、障害のある方たちの雇用を前提とした制度設計を行いました。
ー 自由な働き方にすると、全員が時短勤務を選び、業務に支障が出るのでは?という懸念もあるかと思います。実際のビジネスの現場では、どのように対応されているのでしょうか。
結論から言うと、顧客から非常に高い評価を得ています。というのも、私たちが受注しているのは「重要だけど緊急ではない」仕事だからです。
日揮グループはプラント建設が主な事業で、納期が非常にタイトです。現場の社員たちは日々の業務に追われ、ITによる業務効率化を進めたいと思っても、手が回らない現実があります。
そこで私たちが、その「後回しにされがちだけど重要な仕事」を受託し、ITエンジニアがシステムやツールとして形にして納品するという仕組みです。クライアントからは「やっとこれをやってくれる人が現れた!」という声を多くいただいていますし、社員にとっても、ITスキルを活かしてやりがいのある仕事に取り組めるという点で好循環が生まれています。

ー 阿渡さんはご自身でもSNSやスポーツを通じて発信をされていますね。会社の取り組みの根底には、ご自身のこれまでの体験も大きく影響しているのではないでしょうか。
私自身、生まれつき両腕がありません。けれども、一番の障壁だったのは「社会」そのものでした。多様な人がいるということを、まずは知ってほしい。それが私からのメッセージです。
私が働く多くの社員は精神・発達障害を持つ方々です。正直、私自身もその気持ちを完全に理解することはできません。でも、当事者と対話を重ねる中で「こういう感覚があるんだ」「こんな景色が見えているんだ」と知ることができました。
高校生の頃、初めて社会に出ようとして、アルバイトの面接に50社以上落ちました。理由は見た目です。「君は働けないよね」と言われ続けて、自分が社会から拒絶されているような感覚を覚えました。でも、ある時私は「1ヶ月、無給でいいので働かせてください」とお願いしたんです。給料は要りません。まずは試してくださいと。すると2社が雇ってくれました。
今思えば、それは「雇う側のリスクを下げた」ことだったのかもしれません。同じ時給を払うなら手がある人を選びたくなる、それも理解できるようになりました。だからこそ「話を聞いてみる」「一度試してみる」という姿勢が社会に広がれば、もっと優しい世界になると思っています。
ー 社会全体が「違いを許容する」ことが苦手になってきているように感じます。
ここからは3点、具体的に伺いたいと思います。
① 医療・介護業界などとの連携やITを活用した支援の可能性
② 精神・発達障害のある方の定着率についての現状
③ マネジメントにおける工夫や考え方
この3つについて教えてください。
まず①についてですが、「重要だけど緊急ではない仕事」は、医療・介護を含むあらゆる業界に存在していると思っています。
たとえば人事・総務・財務といったバックオフィス業務の中には、ITやDXの力で改善できるものが多くあります。業界を問わず、やり方次第で障害のある方の力を生かせる場はまだまだあると考えています。
②の定着率についてですが、弊社は非常に高いです。自己都合で退職した社員は現在までゼロです。
これまでに退職された4人の方はすべて会社側からの契約終了で、いずれも「障害への理解が進んでいなかった」「働く準備がまだ整っていなかった」などの理由によるものです。とはいえ、定着率という観点では非常に良好だと感じています。
③のマネジメントについては、現在46人の社員に対して5人のマネジメント層で対応しています。正直、日々いろいろなことが起こりますし、大変なこともあります。でも、フルリモートという働き方が大きな助けになっています。
たとえば、もしオフィスで毎日顔を合わせていたら、お互いの感情がぶつかってしまうこともあるかもしれません。でもリモートであれば、チャットで報告が来たときに、一度深呼吸して気持ちを整理する時間が取れるんです。「さて、また何か起きたな。じゃあどう対処しようか」と落ち着いて話し合える。この“ワンクッション”が非常に大きな意味を持っています。
そして何より、社員との「対話」を大事にしています。精神・発達障害のある方の感じていること、私たちにはわからないことも多くあります。でも、だからこそ認知し、理解しようとする姿勢が大切です。我々は、障害のある方を特別扱いするわけでも、過度に優遇するわけでもありません。ただ、「働く上でのハードル」となっている要素を、できる限り取り除く。その努力を日々積み重ねることが、安定した職場づくりにつながっていると思います。
ー 御社の社名「日揮パラレルテクノロジーズ」の“パラレル”には、すべての人が対等に働ける社会を実現したいという強い思いが込められているとうかがいました。
私たちが今すぐ行動したくなるようなヒントが詰まっていたように感じます。医療・福祉の分野に携わる私たちも、こうしたソーシャルイノベーターの方々と連携し、何ができるかを共に模索していきたい。そんな思いを強く抱きました。本日はありがとうございました。