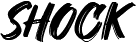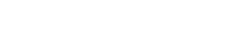
Radio Program
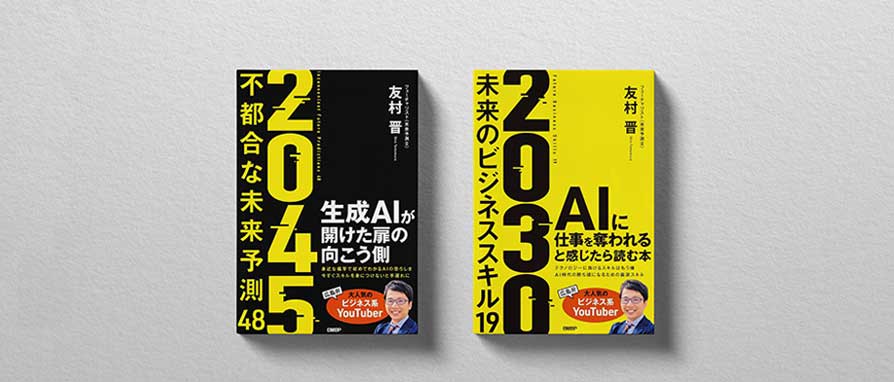
20 Skills to Keep Your Job Safe from AI
AIに仕事を奪われないための20スキルとは?
フューチャーリストが徹底予測2030年〜2045年の未来
Special Guest:TOMOMURA SHIN
スペシャルゲスト:友村 晋さま / フューチャリスト
ー 今回のテーマは生成AIです。本日は『生成AIに仕事を奪われないために読む本』『2030年未来のビジネススキル19』『2045年不都合な未来予測48』の著者で、フューチャリストとして活躍されている友村晋さんをお迎えします。友村さん、フューチャリストとはどんな役割なのでしょうか?
そうですね。あまり一般的な職業ではないと思いますし、実はフューチャリストという言葉には日本語での正式な訳がまだないんです。なので僕自身は「未来予測師」という肩書きを勝手に名乗っているんですけど、特に決まった定義があるわけではありません。
僕が大事にしているのは、パソコンの父と呼ばれるアラン・Kさんの言葉です。「未来を予測する最も簡単な方法は、自らそれを作り出すことである」というものなんですが、この考え方をとても大切にしています。ですので、ただ未来を予測するだけではなく、クライアントの皆さんと一緒にその企業の未来をつくっていくお手伝いをする、という形で活動しています。
ー 生成AIは今、汎用型のAGI(アーティフィシャル・ジェネラル・インテリジェンス)の時代に向かっているとご著書にも書かれていますが、AGIが実現するとどんな未来がほぼ確実に訪れるのでしょうか?
そうですね。本のタイトルにもある「不都合な未来」にもつながるのですが、特にホワイトカラーと呼ばれる業界は大きな影響を受けると思います。例えば、OpenAIのライバルともいえるAnthropic社のクロードというツールがありますが、そこのCEOのダリオさんが「ホワイトカラーの職業の50%が今後1〜5年で消滅する可能性があり、アメリカの失業率が20%に跳ね上がるかもしれない」と発言して話題になっています。これは決して大げさではなく、最前線にいる人たちにはすでにその未来がはっきり見えているんだと思います。
ー AIがこれからさらに進化していく中で、生半可な知識では仕事が奪われる時代が来ると思います。友村さんのご著書でも「生成AIに仕事を奪われないために」というテーマを扱われていますが、これから特にどの業界や分野に注目すべきか、そしてどんなスキルを持つ人材が必要になるのかを教えていただけますか?
まず業界についてですが、生成AIの影響を受けない業界はほとんどないと思っています。もうすでにほぼすべての業界にAIの波は来ていますが、特に影響を受けやすいところにはいくつか共通点があります。
一つは「〇〇テック」というキーワードがすでに浸透している分野です。例えば教育業界では「EdTech(エドテック)」、金融業界では「FinTech(フィンテック)」というように、テクノロジーと結びついている業界は、テクノロジーの波がこれからもどんどん押し寄せてくる可能性が高いと言えます。相性が良いということですね。
もう一つは、その市場規模が大きいかどうかです。例えばFinTechの分野は市場規模が非常に大きいので、そこに向けてソフトウェアやツールを開発して市場を取ってしまえば一気に大きな利益を生み出せる。だからこそ世界中の企業が、一攫千金を狙って競争に参入してきます。結果として、その分野ではより高品質なツールがどんどん出てきて、そこで働く人たちはより淘汰されやすくなる可能性が高いんです。
次にスキルについてですが、僕の本の中では19個プラス1個、合計20個のスキルを挙げています。その中でも特に大切だと思っているのが「一時情報収集力」です。一時情報とは、自分が実際に体験して得た一次的な情報のことです。ネットに転がっている二次情報や三次情報ではなく、自分自身の五感を使って集めたリアルな情報ですね。
なぜこれが大切かというと、生成AIは基本的にネット上の既存の情報をつなぎ合わせることしかできません。そうするとブログやSNS、ウェブサイトなどの情報がどんどん似通ってきて、誰が書いても同じようなものになり、情報がコモディティ化していきます。そのときに「誰が一次情報を持っているのか」ということが、これからの社会ではとても大事になると思っています。だからこそ、これまで以上に自分の足で動いて体験し、自分の言葉で語れる力を磨いておくことが、AIに仕事を奪われないために必要なスキルになると考えています。
ー 今お話にあった「一時情報」についても、本の中でいくつか具体的に紹介されていますが、エストニアでは確定申告がないんですよね。テクノロジーの進化によって、そもそも税理士という職業自体が存在しないというのは、とても象徴的だと思います。
そうですね。正確には確定申告という作業自体はあるのですが、日本のように年に一度の大きなイベントにはなっていません。税理士さんも全くいないわけではないのですが、日本のような形での税理士業務はほとんどなくなっているんです。どういうことかというと、エストニアではマイナンバーカードの普及率が99%で、すべての口座がひも付いていて、税務署と政府がすべてのデータを把握しています。
だから企業や個人の売上や経費、利益まで把握できていて、「あなたの利益はこれだけなので税金はこれ だけですね」という内容がメールで送られてきます。そして「イエス・ノー」で答えて、イエスを押すと口座から自動で引き落とされて確定申告が終わる仕組みです。もし異議申し立てがある場合にだけ税理士の出番があるという感じです。実際に現地で税理士の人たちに「今は何をしているのか」と聞いたら、ほとんどの人が財務のコンサルタントなど、より付加価値の高いアドバイス業務にシフトしているという話でした。

ー 友村さんの著書でも触れられている「AIを活かすには人間力が大事」というお話がありましたが、そのヒューマン的な問いを投げる力について、改めてリスナーの皆さんに教えていただけますか?
そうですね。これは東大の松尾豊さんの本の中にもあったフレーズで、僕自身とても印象的に覚えているんですが、「AIを知るとは、人間を知ること」という言葉があるんです。松尾さんはAI研究の世界でもトップランナーとして活躍されていますが、その本の中で「AIを勉強すればするほど、人間って何なんだろうって考えてしまう」と書かれていて、すごく共感しました。
結局、AIと人間の違いは何かという問いに、はっきりとした答えはなくて、哲学的な話にもつながっていくと思うんです。ただ、仕事やビジネスに関して言えば、こういう問い自体を持つことがとても大事だと思っています。
例えば、職場でちょっとムカつく上司って時々いるじゃないですか。その上司の言っていることが、どれだけ正論で正しくても、ムカつくから言われた通りにしたくないっていう感情が人間にはありますよね。AIだったらそんなことは絶対にない。正しいことを言われたらその通りにするはずです。
でも人間はそうじゃない。そこにこそ、人間が人間である証明のようなものがあると思うんです。AIがどれだけ進化しても、私たちは仕事でもプライベートでも、家族や恋人との関係でも、感情や人間関係で物事を選択していきます。
だからこそ、ビジネスの現場でもAIがすべてを代替するわけではなく、最後の「人間らしさ」が活きる部分が必ず残ると思っています。ヒューマン的な問いを投げる力、人間だからこそ生まれる矛盾や感情の機微、そういうものにこそAIにできない隙間があって、そこに僕は大きなヒントがあるんじゃないかなと思っています。
ー 本書では「ビジネススキル19」に加えて、書籍のQRコードからシークレットスキルの20個目も見られるんですよね。また未来予測も48に加えてシークレットの49個目がありますが、実際にここまでたどり着いている方は意外と少ないとお聞きしました。
そうなんですよ。本当にすごくショックだったんですけど、僕は本を買ってくださった方は当然、最後まで読んでQRコードも見てくれるものだと思っていたんです。でも実際には、本の途中で読むのに疲れて離脱してしまっているのか、それともQRコードの存在に気づいていないのかわからないんですけど、思った以上にシークレットの動画までたどり着いている方が少なくて、正直残念に感じています。
特にこのQRコードの先の動画は、すごく気合いを入れて作った内容なんです。なので、もし今お手元に本をお持ちの方がいらっしゃったら、ぜひ巻末にあるQRコードを読み取って、シークレットスキルの20番目や未来予測の49番目まで、ぜひ最後まで楽しんでもらえたら嬉しいです。
ー そうですよね。動画を見ていないのは、衝撃的な未来を知って思わず本を閉じてしまった方もいるかもしれませんね。医療・介護分野についてはどうしても人の力が必要な部分が多いので職業自体はなくならないと思う一方で、入力作業の電子化やAIによるケアプラン作成などは進んでいくと思います。人の手によるケアとのバランスについて、友村さんはどうお考えですか?
僕も本当にほとんど同じ意見で、医療や介護という業界自体がなくなることは絶対にないと思っていますし、むしろこれからますます必要になっていくと思います。ただし、いわゆる「ひな形仕事」はどんどんAIに置き換わっていくので、業界の市場が大きくなるからといって、そこで働く人が単純に増えるとは限らないと考えています。
それから、1年くらい前にチャットGPTのセミナーで話したときは、「ひな形仕事はなくなるけれど、介護現場で働くメンタルケアの相談に乗る人のような仕事は残るだろう」と言っていたんです。でも、正直ここ1年で僕の考え方は少し変わってきています。それは、チャットGPTの進化を見ているからなんですけど、最近のAIはメンタルケアの相談もプロ並み、あるいはプロ以上に対応できるようになってきています。
1年前まではAIの回答はロボット的で、相手の気持ちに寄り添うような感じではなく、聞かれたことだけを正確に答えるだけだったので、メンタルケアとしては到底無理だと思っていました。でも、最近のチャットGPTと会話してみると、話し方がとても自然になっていて、本当に寄り添ってくれるんです。しかも、「えっと」とか「あー」とか、人間っぽい間を入れながら話すようになってきていて、例えば「それなら無理しないで、プロの専門家に相談してみてもいいかもしれませんね」とか、優しい言い回しをするんですよ。
これを見ていると、1年後にどうなっているのか本当に予測がつきません。映画『her/世界でひとつの彼女』のように、AIに恋をする時代が現実になる可能性もあると思っています。特にメンタルケアだけじゃなくて、プライベートでも、例えば友達や恋人としてAIと付き合う人が増えてくるんじゃないかと。人間はときには上司や家族から厳しいことを言われてメンタルがしんどくなることもありますが、AIは自分にとって都合のいい存在でいてくれるので、そちらに安心感を求める人は確実に増えると思います。
話を介護に戻すと、高齢者の方が自分専用のAIが自分のパーソナリティを学習して、寄り添った会話をしてくれて、さらにバーチャルアバターがリップシンクして口の動きも自然で、表情も豊かに動くようになれば、本当に目の前で人と話しているような錯覚に陥ることも可能になるでしょう。そうなると、これまで人間にしかできなかったケアの一部も、AIに置き換わっていくかもしれないと考えています。
では介護の中でどんな仕事が残るのかというと、やはりマネジメントの部分だと思います。メンタルケアは1対1なのでAIでも対応できるようになってきていますが、マネージャーは違います。多くの利用者さん、スタッフ、そしてAIなど、複数の要素を同時に把握しながら、それぞれの状況に合わせて適切に判断し、支えていく必要があります。これはパラメータが多すぎて、今のところAIには簡単に置き換えられないと感じています。
ですから、これからの時代に介護の現場で本当に必要になるのは、AIでは補えない複雑な調整や人間関係のマネジメントができる人材なんじゃないかと思います。

ー 本書でも触れられていましたが、「AIは使わないほうがいい」と言う人の意見に引っ張られすぎず、自分はどうするかをしっかり考えたほうがいいということですね。
そう思います。AIを使うことは、もはやパソコンでタイピングができるのと同じか、それ以上に重要なスキルです。だから「使わない」という選択肢自体が、今の時代ではありえないと思います。
ー 今年に入って特にチャットGPTなどの生成AIが一気に便利になりましたが、友村さんの本を読むと、将来のASIの時代には「人類はこんなことで悩んでいたのか」と思うほどの進化が来るかもしれないと感じます。AIはまるで現代の神のような存在になる、そんな未来を意識しておいたほうがいいんですね。
そう思っておいた方がいいと思います。今の話はすごく大切で、実際に僕がYouTubeでこういう話をすると、「そんな未来が来るわけがないじゃないか」とか「もし外れたらどうするんだ」っていう、いわゆるアンチコメントを結構いただくんです。でも僕はいつも、そのコメントに対して必ずお返ししていることがあります。それは、「僕の予想が当たるかどうかは正直どうでもいい」ということなんです。
大事なのは、そんな未来が来るかもしれないと想定して、逆張りして今のうちに自分のスキルを磨いておくことだと思っています。もし未来予測が当たったら「磨いておいてよかった、ラッキー」って思えるし、もし仮に外れてそんな未来が来なかったとしても、自分を高めるために磨いてきたスキルは絶対に無駄にはなりませんよね。
つまり、当たるか外れるかにこだわるよりも、「そんな未来が来るかもしれない」と考えて行動しておいた方がいいんです。何のデメリットもないですし、むしろ備えておいた方が確実に得られるものがある。だからこそ僕は、そういう考え方で逆張りしておくことが大事なんだと伝えています。
ー 最後に未来に向けて何か行動を起こしたいリスナーの皆さんへ、ぜひ一言メッセージをお願いします。
これは僕の『AIに仕事を奪われないために読む本』の中でも特に大切にしているスキル19番目の話です。本の中では、スキル1番目から18番目まで読んでくれた人に対して「これらを全部束にしても、最後の19番目にはかなわない」と前置きして書かせてもらいました。
その19番目とは何かというと、「ウェルビーイング」です。自分で自分の幸せを感じられる力ですね。これをスキルと言っていいのか分からない部分もありますが、僕はこれからの時代に一番大切な感覚だと思っています。
「ハッピー」というのは一時的な幸福を指しますが、「ウェルビーイング」は生きているだけで幸せと思える状態のことをいいます。これから先、世の中はますます変化が激しくなっていくと思います。これまでの常識が非常識になったり、逆に非常識が急に常識になったりして、精神的にも不安定になりやすい社会を私たちは生きていくことになります。
そんな中で、自分にとっての幸せは何かを早めにしっかり定義しておかないと、変化の波や生成AIの波にただ飲まれてしまって、必要以上に不安や不幸を感じてしまう機会が増えてしまうと思うんです。
例えばですが、「私はこの場所に住んで、これくらいの収入があれば十分幸せ」というように、人と比べずに自分にとっての幸せの基準をしっかり持っておく。これが、これからの時代を安心して生き抜いていくために本当に大切なことなんじゃないかと思っています。
ー ぜひ友村さんのYouTubeやご著書を通じて、未来を予測し「怖くない、むしろ味方につければ素晴らしい未来が待っている」と感じていただければ嬉しいです。本当にありがとうございました。