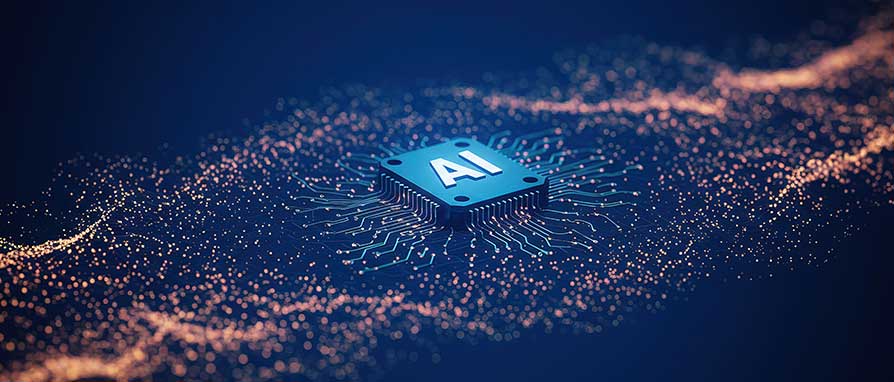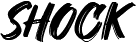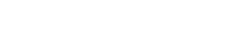
Radio Program
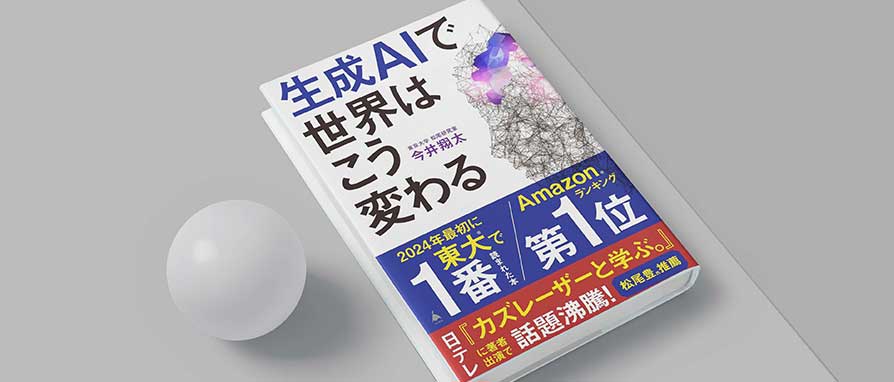
Genius Is No Different from the Ordinary.
凡人もアインシュタインも差はない
「AIネイティブ」の時代ー人類の歴史が変わる瞬間に希望を持って立ち会う
Special Guest:IMAMURA SHOTA
スペシャルゲスト:今井 翔太さま / 北陸先端科学技術大学院大学 客員教授
ー 本日は"2024年の初め、東京大学で最も読まれた本"としても話題の『生成AIで世界はこう変わる』の著者であられます北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)客員教授今井翔太先生をお迎えしています。本書は2024年1月に発行され、もう1年半が経過しています。終章では先生が「もしこの本の内容がすぐに時代遅れになったとすれば、それは生成AIが世界を変えるという本書のメッセージが実現したということだ」と書かれています。この1年、いかがでしたか?
本当にすごく変わったんです。
例えば、この本を書いた当時もそうでしたが、ちょうど1年前、私がラジオ番組に出演していたら、「今の生成AIは東大には合格できませんよ」と言っていたはずなんですね。でも、今はどうかというと、たった1年ちょっとで、東大に合格できるどころか、トップ層の成績で合格できるレベルにまで到達してしまったんです。
使われている技術自体が、私が本を書いていた頃にはまだ存在していなかったものも多く、本はまだ売れてはいますが、正直、想定していなかった技術が次々と登場している状況です。
そういった意味では、「生成AIが世界を大きく変える」という当時のメッセージは正しかったのではないかと、自分でも感じています。
ー 本書では、ChatGPTの前身であるGPT-3(2022年公開)までが扱われていましたね。そこから莫大な投資が進み、NVIDIAの株価も上昇するなど、急速な発展が見られました。ChatGPTの登場後、GeminiやClaudeなどが次々に現れた背景も、本書を通じて理解できました。この1年で、当時は想像できなかったような技術も登場していますが、その点についてもご説明いただけますか?
はい、大きく分けて2つあります。
1つ目は、「推論能力を持った生成AI」です。正確に言うと、技術の“種”は当時からあったんですが、当時のAIは、難しい問題を与えると、突然答えを「バーン」と出して終わりという感じだったんです。でも人間は、与えられた問題に対して、じっくり思考を巡らせて、「これが正しいと思います」と答えを出す。この“思考の過程”が、当時のAIには欠けていた。
とはいえ、「Let’s think step by step.」といったプロンプトを与えることで、当時のAIも思考プロセスを踏むことはできました。これは、私が所属していた松尾研究所が研究し、世界で最も読まれたプロンプト研究の一つにもなったものです。
ただ、現在の生成AIは、最初から推論能力を備えていて、東大の入試問題のような長文の問題に対しても、自分の思考を文章で展開して、途中の式や考えの変化もすべて出力して、最終的に正しい答えにたどり着くことができるようになっています。この能力は、2024年後半から急速に発展して、今も進化中です。
2つ目は、「AIエージェント」と呼ばれる技術です。これは皆さんも最近よく耳にされるかと思いますが、実はこの技術自体はすでに当時から存在していたんです。ただ当時は、せいぜい人間が5分かけてやる作業をなんとか真似できるかどうか、というレベルでした。ところが今では、人間が数時間かけて行っているような複雑な作業を、自動的にこなせるレベルにまで来ています。
AIが検索ツールやオフィス系ツールなどを使いながら、指示を受けて一連の作業をこなしてしまう。まさに“エージェント”としての能力が飛躍的に進化しているのです。今後は、2030年や2031年には、人間が1ヶ月かけていた作業を自動化できるようになると言われています。
この分野の進化は本当に目覚ましいですね。
ー AI研究者の間では、これらの技術はいずれやってくるであろう、確かな未来だと考えていたのでしょうか。
そうですね。私が本を書いていた当時から、AI研究者は「時間の問題だ」と考えていました。今起きていることは、いずれやってくるものだったという認識は変わりませんが、これほど早く実現するとは思っていませんでした。
ー 生成AIの進歩は非常に速く、1年前と今では話している内容が全く違うのが現実だと思います。AIをうまく活用できなければ多くの職業が脅かされ、今後1〜2年で個々のスキルアップが必須になるでしょう。先生は、この状況をどうお考えでしょうか。
技術はさておき、皆さんに一度歴史の教科書を引っ張り出していただきたいと思います。産業革命をはじめ、歴史を大きく変える革命はたくさんありました。そうした革命の前と後では社会の状況が一変し、対応できなかった人々は苦境に陥りましたが、社会全体としては大きく発展しました。
今起きていることは、そのレベルと同じ、いやそれ以上です。人類が誕生してから30万年の歴史の中で、最も重要なことが起きていると言えます。産業革命すら比較にならないほどの出来事が今、起きているのです。
危機感という言葉もそうですが、今は人類史における非常に特別なイベントが起きているという認識を持つことが重要です。端的に言えば、人類より賢い存在が今、現実に出現しているのです。我々ホモサピエンスは30万年間、地球上の知能の王者でしたが、自分より賢い存在が誕生するのをリアルタイムで目撃しているのです。これは人類史上初めての経験であり、2022年から2025年を生きる我々が唯一その瞬間を目撃できるのです。
そうした意識を持って、AIのスキルを身につけることはもちろん、仕事や社会構造そのものに対する考え方も改めなければならないでしょう。

ー 著書では「超知能」という言葉でご紹介されていますが、これは「凡人とアインシュタインの差すらも無意味になる」ということですね。
その通りです。科学者やプログラマーは今、それを実際に体験しています。アインシュタインが1時間に100本の論文を読めるとします。私は1本読むのがやっとかもしれません。しかし、今のAIは1時間に1万本の論文を読めるでしょう。1万本読めるAIから見れば、100本読めるアインシュタインも1本しか読めない私も、大差はありません。
これは、根本的に人間とは異なる知能が出現していることを示しています。機械の知能と、タンパク質でできた人間の知能は、質的に全く異なるものなのです。機械は生物学的な制約に縛られることなく、様々なことができるようになります。科学者が経験しているこの世界が、今後、普通の人々の社会にも入り込んでくるでしょう。
ー 今でも「ハルシネーション(嘘をつくこと)」が指摘され、大規模言語モデルは感情を持たず、単なる単語予測の繰り返しだという議論も耳にします。この点はどうお考えですか?
残念ながら、これはどうしようもない部分があると思います。ホワイトカラーの仕事がある程度代替され、あるいは奪われるということは、もはや止められない流れだと個人的には考えています。実際に、ある会社がAI導入によって何千人ものソフトウェアエンジニアを削減したという報道も目にします。これはすでに起きている現象であり、今後も止まらないでしょう。
それでも、人間には役割があります。長年人間の体で生きてきたからこそ、現実世界を円滑に動き回れるという強みです。この強みを活かすような、あるいは高い倫理観や責任が問われるような仕事は、AIに代替されにくいでしょう。もし今、仕事を奪われるかもしれないとネガティブな感情を持っている方がいるなら、そうした視点に仕事を変えることを考えてもいいかもしれません。
ー 医療・福祉分野は人手が必要なので、AIにすべてが侵食されるわけではないと思います。ただ、2040年までに60万人の働き手が不足すると予測されており、この人手不足を補うため、ケアプラン作成などをAIで自動化してコスト削減するのは十分に考えられますがいかがでしょうか。
おっしゃる通り、日本のように人口が減少している国では、「仕事が奪われる」と考えるのではなく、「人が足りていない」という視点が重要です。そう考えれば、AIの導入は恐怖ではなく、必須のものだと捉えることができます。
人口統計を見れば、将来的にどうなるかはある程度予測できます。その数字を冷静に見れば、特別な対策をしなければ社会が維持できないと誰もが感じるでしょう。そうした意識を共有すれば、AIの導入はむしろ不可欠なものになります。台湾の元デジタル担当大臣であるオードリー・タンさんも、日本のような人口減少国の方がAIを積極的に導入するモチベーションが高く、長期的に見れば豊かになるだろうと述べています。
介護や医療の領域では、ヒューマノイドロボットが重要になってくるでしょう。現在、その研究は急速に進んでいます。かつては、人間が行う肉体労働はAIには難しいと考えられていました。しかし、将棋でプロに勝ったり、研究者レベルの文章を書くAIの方が先に誕生しました。これは、文章データや論文など、AIが学習できるデータが膨大にあったからです。
今、肉体労働も同様にデータを集める動きが出ています。東大の松尾研究室では、人間がロボットを操作する際の動きのデータを集め、世界中で共有しています。この流れを見れば、介護ができるヒューマノイドロボットも近い将来、5年ほどで登場するかもしれません。日本は人口減少に対応するために、こうした技術を積極的に受け入れ、ポジティブに発展していくのではないでしょうか。

ー ホワイトカラーの職業がAIに脅かされることが恐怖として捉えられているのは、良い大学を出て安泰だと思っていた人々の職業が、真っ先に奪われる可能性があることがこの2、3年で明確になったからではないでしょうか。この点について、先生はどう捉えていますか。
残念ながら、ホワイトカラーの仕事がある程度AIに代替される、あるいは奪われるという流れは、個人的には止められないと思います。実際に、AI導入によって何千人ものソフトウェアエンジニアを削減した企業があるという報道も目にします。これはすでに起きている現象であり、今後も止まらないでしょう。
それでも、人間には役割があります。長年人間の体で生きてきたからこそ、現実世界を円滑に動き回れるという強みです。この強みを活かすような、あるいは高い倫理観や責任が問われるような仕事は、AIに代替されにくいでしょう。もし今、仕事を奪われるかもしれないとネガティブな感情を持っている方がいるなら、そうした視点に仕事を変えることを考えてもいいかもしれません。
ー 最後に、先生からメッセージをお願いします。
「AIネイティブ」になろう、というメッセージを伝えたいです。これまでの社会は人間を前提にした仕組みがたくさんありました。階段や椅子がそうであるように、業務や組織、インターネットの仕組みも、人間のために設計されています。しかし、この前提をひっくり返す必要があります。
もちろん、個人レベルで全てを変えることはできません。しかし、普段の仕事や考え方にも、人間を前提にしたものがたくさんあるはずです。ぜひそれをひっくり返し、AIを前提とした思考で物事を捉えていただきたいと思います。
新しい技術が登場する際には、その技術を前提に考えた人が勝つ、と言っても過言ではありません。アマゾンの創業者ジェフ・ベゾスは、もともと小売や書籍販売の専門家ではありませんでしたが、インターネットという技術を前提にビジネスを設計することで、Amazon帝国を築き上げました。
このように、新しい技術を前提に何かを設計する「ネイティブな思考」を持てば、その分野の第一人者になれる可能性があります。仕事を奪われるというマイナスな話ではなく、AIという新しい技術が生まれたからこそ、それを前提にした考え方で多くのチャンスをつかんでほしいと思います。
ー 先生のご著書『生成AIで世界はこう変わる』を読めば、今起きていることへの理解が深まります。本書にある「アイデアさえあれば何でも実現できる」という言葉の通り、恐怖ではなく、未来を明るく捉えることが重要だと感じました。本日は貴重なお話をいただき、本当にありがとうございました。