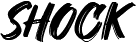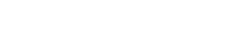
Radio Program

The End of Money-Lending Banks.
カネを回すだけの銀行は終わる
──高知発!価値共創の拠点たる地域金融機関が描く未来地図とは
Special Guest:KAWAI YUKO
スペシャルゲスト:河合 祐子さま / 株式会社 高知銀行 取締役頭取
ー 本日のゲストは、高知銀行の取締役頭取、河合祐子さんです。京都大学を卒業後、JPモルガン・チェースや日本銀行を経て、2023年に高知銀行の頭取に就任されました。就任にあたってのお気持ちをお聞かせいただけますか。
ご紹介いただきました通り、私は高知銀行に2023年に副頭取として入行し、2年ほど勤めた後、株主総会でご承認いただき、頭取となりました。副頭取から頭取になったことで、何か新しいことを始めるのかと聞かれることが多いのですが、副頭取時代からやりたいことは特に変わっていません。
それは、現在進行中の中期経営計画で掲げている「人」「事業」「財」、いわゆる人物金を、お客様と高知銀行の両方で大事に育てていくことです。中でも「人」を大事にすることが非常に重要だと考えています。お金や事業サービスも大切ですが、何よりも人が幸せであることこそが、第一の目的であるべきではないかと。これは都会よりも地方で、より重要になる気がしています。人の幸せを実現するために、財務や事業も大切にしていくという発想で、これからも取り組んでいきたいです。
ー 地方銀行で初めての女性頭取としても注目されています。外資系金融機関にご就職されたご経験も大変ユニークですが、どのような思いで海外の金融機関に飛び込まれたのでしょうか。
私が社会人になった1987年当時、外資系金融機関に新卒で入社するのは珍しかったかもしれません。しかも、私は当時英語がほとんど話せなかったので、かなり無謀でしたね。
なぜ外資系を選んだかというと、当時は男女雇用機会均等法が施行されて1年目で、多くの会社が女性をキャリアとしてどう活用するかのイメージを具体的に持てていない印象でした。そんな中で、女性のキャリアを使い慣れている外資系金融機関であれば、不安なく働けると考えたのが理由です。
ー その後、日本銀行に移られた際には、カルチャーの違いに戸惑われたのではありませんか。
そうですね。仕事の内容はもちろん、民間のセクターから公共のセクターに移ったので、そもそも会社が目的にしていることが違いました。また、アメリカの組織から日本らしい組織に移ったことで、言葉遣いや上司への接し方、意思決定の手順などもだいぶ違うなと感じました。ただ、仕事で成果を上げるということ自体は変わりがないので、どうやって成果を上げるかに集中し、やり方の違いを乗り越えていきました。

ー 高知銀行の頭取になられたきっかけは、日本銀行時代に高知支店で働かれたご経験にあると伺っています。なぜ、地方金融機関のマネジメントとして新たな世界に飛び込もうと思われたのでしょうか。
おっしゃる通り、日本銀行時代に高知支店で働いたことが高知との出会いです。もともと静岡の出身なので、地方に馴染みがないわけではありませんでしたが、いつか日本の地域で働けたら良いなと思っていました。高知支店で、高知の人や企業の方々、社会文化に触れて、ここは本当に素敵なところだと感じました。規模は小さい社会ですが、だからこそできることもあるのではないかと。そう思っていたら、このような機会をいただきました。
ー 高知銀行が地域で果たすべき役割や、注力されている取り組みについてお聞かせください。
銀行は、社会が変化すれば、そのあり方も変わってきます。皆様に安心安全をお届けするインフラとして転換しにくい業態ではありますが、お客様が変化すれば、サービスも変化するのは当然のことです。
なぜ大きな変化かというと、一つは人口減少ですが、それ以上にデジタル化の進展があります。昔のように、あるグループ全体に画一的なサービスを提供するのではなく、今は一人ひとりの個性に合わせたサービスを提供する必要があります。また、単品ではなく、お客様のご事情に合わせて様々なものを組み合わせたソリューションをお届けする時代になっています。
これまで銀行は、預金・融資・送金という基本的な機能を持っていましたし、お客様の家族構成やご年齢といったざっくりとしたプロファイルのもとに、定型的で画一的なサービスを提供してきました。しかし今は、個人のお客様であれ、企業のお客様であれ、それぞれのご事情に合わせて、どんなソリューションを提供すべきか知恵を絞らなくてはいけません。今これに注力しています、というよりも、お客様のご事情を伺って、求めておられるものを提案できる銀行になることを目指しています。
ー より金融機関の皆さんが地域に寄り添い、専門的な知識や知恵を絞ることが、これからの地域金融機関のあるべき姿ということでしょうか。
私はあまり「寄り添う」という言葉を使いません。なんとなく上から目線のような気がするからです。どちらかと言えば「共に働かせていただく」というイメージが近いかもしれません。
おっしゃる通り、金融に正解はありません。一人ひとりのご事情に合わせて解決策を考えなければなりませんし、世の中がより複雑になっているので、お客様のお話をより丁寧に聞いていく必要があります。
これはよく引用する言葉なのですが、マイクロソフトのビル・ゲイツ氏が30年も前に「銀行業は必要だが、銀行は必要ない」と言いました。この言葉に私たちは向き合わなければなりません。スマートフォンが一人一台のコンピューターになった今、金融サービスは本当に銀行でないと提供できないのか。この問いにきちんと向き合い、それでも「やっぱり銀行に頼っていただきたいです」と言うためには、私たちもよくよく考えていかなければいけないのです。

ー 若年層の金融リテラシーが向上し、起業も増えています。地方発のスタートアップ企業との連携など、若者との取り組みはされていますか。
起業する、つまり自分で業を起こすということは、給与所得者とは全く違うレベルです。自己資金だけで会社を起こせるわけではないので、お金の心配は常にしなくてはなりません。こういうところに銀行がサポートできるのではないか、と私たちは考えています。
そのため、スタートアップ企業の方々とお話をするのは積極的にやろうと考えていますし、すでにやり始めています。地域には、スタートアップの人たちが集まるネットワーキングやイベントがいくつかありますので、そこに積極的に売り込みに行っています。「銀行のおじさん、おばさんと話したことがない」という人たちと早い段階でつながりを持てるようにしています。
ー 地域金融機関で働く方々の中には、すぐに結果が出ない事業への取り組みに、モチベーションを保つのが難しいと感じる方もいるかもしれません。職員の方々の心に火を灯すために、どのような取り組みをされていますか。
経営学の共通のテーマに、「イノベーションのジレンマ」があります。既存の事業を深めることと、新しいイノベーションを起こすことは、どちらも重要です。これは、銀行の業務についても、お客様との関係についても同じです。
既存事業は結果が出やすい一方、イノベーションは結果が出にくい傾向があります。結果が出にくい人たちのモチベーションをどう維持するか、逆に結果を出している人たちが彼らにどのような思いを持つか、ここが経営の役割です。正解はありませんが、多くの場合、得意分野に合わせて担当を分けるという方法を取ります。
ー つまり、結果がすぐに出ないからこそ頑張れるというモチベーションを持つ必要がある、ということでしょうか。
ありがとうございます。私自身、毎日自分に言い聞かせていることがあります。それは、「イノベーションを起こすことを目的にしない」ということです。
DX(デジタルトランスフォーメーション)も同じで、DXを目的にしたDXは、大抵成功しません。本質的に「何を実現したいのか」という目的が明確でなければ、変化は長続きしません。目的を達成するために今やっていることが最善であればそれを磨き上げ、そうでなければイノベーションを起こせば良いのです。だからイノベーションのジレンマもあるんですよね。そこは誤解をしないようにしたいと、常に自分に言い聞かせています。
ー 地方銀行の存在は、これからもますます重要になっていきます。河合頭取のような経験を持った方がトップにいらっしゃることで、高知銀行の職員の方々のモチベーションが日々高まっていることと実感しました。本日はありがとうございました。