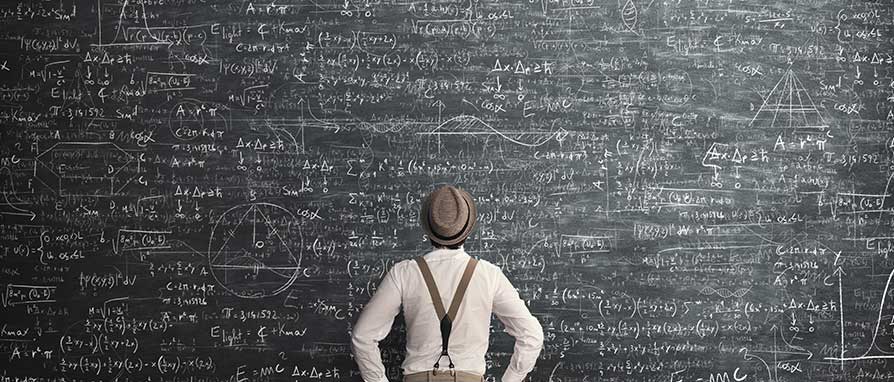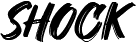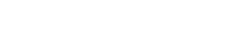
Radio Program
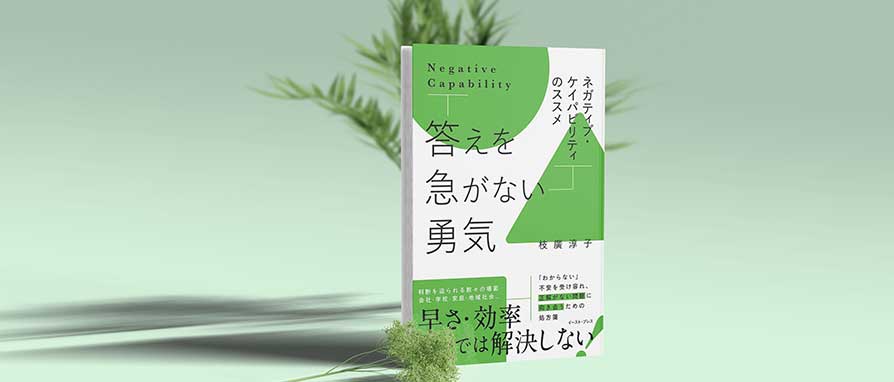
Negative Capability
ネガティブ・ケイパビリティ
「答えを急がない勇気」が社会を変える──意思決定を支える「もうひとつの能力」
Special Guest:EDAHIRO JUNKO
スペシャルゲスト:枝廣 淳子さま / 大学院大学至善館 副学長・教授
ー 本日は、大学院大学 至善館の副学長・教授である枝廣淳子先生をお迎えしています。先生は環境ジャーナリスト、翻訳家、そして教育者として多方面で活躍されており、著書も多数ご出版されています。今回の対談で伺いたいのは「ネガティブ・ケイパビリティ」についてです。先生のご著書『答えを急がない勇気 ネガティブ・ケイパビリティのススメ』(イースト・プレス)でも詳しく書かれていますが、今こそ多くの方に知っていただきたい重要な概念だと思います。枝廣先生、「ネガティブ・ケイパビリティ」とは何でしょうか?
ネガティブ・ケイパビリティって、本当に不思議な言葉ですよね。ケイパビリティというのは「能力」という意味で、何かができる力のことを指します。そこに「ネガティブ」がついているという、ちょっと変わった組み合わせの言葉なんです。これは、何かを“しない”才能、あるいは能力、というふうに捉えられます。私たちはどうしても、すぐに答えに飛びついたり、ぱっと判断してしまったりしがちですよね。でもそうではなくて、その場でじっと持ちこたえる、すぐに白黒つけずに考え続ける、そういう力のことを「ネガティブ・ケイパビリティ」と呼んでいます。
ー ネガティブ・ケイパビリティは、何かをあえてしない力や、不確実さに耐える力、多様で矛盾した考えを受け入れる力とも言われます。こうした力が、今の時代に必要とされるのはなぜでしょうか?また、これはAIにはない、人間だけの能力と言えるのでしょうか?
そうですね。コンピューターや人工知能は、プログラムされた通りに動くもので、自分の意思で立ち止まったり、すぐに答えを出さずにあれこれ考えを巡らせたりすることは、今のところまだできないと思います。ですので、ネガティブ・ケイパビリティはとても人間的な力であり、今の時点では人間にしか発揮できない、大切な能力だと感じています。
ー 先生はこのご著書を通じてネガティブ・ケイパビリティの大切さを伝えておられますし、先生ご自身の多岐にわたるご活躍の根底にも、この力があるのだと感じています。そこでお伺いしたいのですが、日本、あるいは世界では、このネガティブ・ケイパビリティという言葉自体、どれくらい知られているのでしょうか?また、能力として身につけている人は、実際どのくらいいるのでしょうか?
言葉として「ネガティブ・ケイパビリティ」を知っている方は、まだあまり多くないと思いますね。一般に「ケイパビリティ」と言うと、前向きに何かを成し遂げる力、つまり「何かができる能力」をイメージされる方が多いのではないでしょうか。
たとえば、情報を集めて分析し、予測して計画を立て、それを実行していくような力。特にビジネスの現場では、そうした前へ進む能力を「ケイパビリティ」と呼ぶことが多いです。私たちはそれを「ポジティブ・ケイパビリティ」と表現しています。実際、サクサク仕事をこなすためにはこの力がとても大切で、情報収集、検索、要約、予測などの場面では、生成AIも非常に役立つと思います。
一方で、私たち人間は、すべてが見えているわけではありません。見えている範囲だけで判断したり、結論を急いだりすると、結果として的外れになってしまうこともある。だからこそ「ちょっと待てよ」と立ち止まる、その姿勢こそがネガティブ・ケイパビリティだと言えると思います。この言葉を知らなくても、そうした対応を自然に実践している方は、意外と多いのではないでしょうか。
それに、日本語にはもともと「急がば回れ」や「慌てる乞食はもらいが少ない」といった表現がありますよね。拙速な行動を戒める言葉は昔からたくさんあります。それを今風に、少し理論的に整理したものがネガティブ・ケイパビリティ、というふうに考えていただくと、わかりやすいかもしれません。

ー ポジティブ・ケイパビリティとは対極にあるように見えますが、両者は排他的ではないですよね。どちらも大切で、まさに車の両輪のような関係だと考えていいのでしょうか?
そうですね。ポジティブ・ケイパビリティは物事を前に進める力で、車にたとえるなら“アクセル”のようなものです。一方で、立ち止まって「この方向でいいのか」「必要な情報は揃っているか」「周囲の合意はあるか」と確認する力――それがネガティブ・ケイパビリティで、いわば“ブレーキ”の役割です。
ブレーキのない車に乗るのは怖いですよね。それと同じで、ポジティブかネガティブか、どちらが良いかというよりも、どちらも道具箱に入れておくべきだと思います。日々のルーチンワークではポジティブ・ケイパビリティで進めればいい。でも例えば、元気のない部下の話を聞くときや、子育てで迷うとき、大きな判断を求められるときなどは、ネガティブ・ケイパビリティが必要になる場面です。
「ちょっと待てよ」と立ち止まって、今ある情報だけで決めてしまわずに、より深く、より広く考える。そのための力がネガティブ・ケイパビリティであって、思考を止めるわけではなく、より良い選択のために使うものなんです。そういう意識を持っていただけるといいなと思います。
ー ネガティブ・ケイパビリティは、詩人キーツが「不確実さや疑いの中に安らかにとどまる力」として語ったように、すぐに答えを出さずに考え続ける力だと感じました。これからの時代、AIが明確な答えを出す一方で、人間にはこの“待つ力”がより求められるのではないでしょうか。またネガティブ・ケイパビリティを育てていくうえで、「ディスパーサル(散らすこと)」と「コンテインメント(受け入れて保つこと)」というキーワードが重要だと本書にも書かれていました。まずこの2つについて、どのように理解すればよいか教えていただけますか?
「ディスパーサル」というのは、あまり耳なじみのない言葉かもしれませんが、「散らす」という意味です。たとえば「この答えで本当にいいのかな」「もしかしたら答えは見つからないかもしれない」――そんなふうに感じると、不安やモヤモヤが生まれますよね。私たちは普段、すぐに決めて前に進むことに慣れているので、この居心地の悪さに耐えるのが苦手なんです。
だからこそ、「とりあえずこれで行こう」と答えを急いで決めたり、最初に見えたものや思い込みに飛びついたりして、その不安を「散らそう」とします。この動きが、まさにディスパーサルです。これは人間のごく自然な反応で、脳は「よく分からない状態」を脅威として感じるため、なるべく早く消そうとするんですね。
でも、それによって思考が止まってしまいます。「これはこういうことだ」「この人はこういう人だ」と決めつけてしまうと、それ以上考えなくなってしまう。そういうときに必要なのが、ネガティブ・ケイパビリティです。
「コンテインメント」は、「器」や「包み込む」といった意味があります。自分の中にある不安やモヤモヤに気づいて、「あ、今私は不安なんだな」「答えが見つからなくて落ち着かないんだな」と客観的に自分を見つめ、受け入れる。そうすることで、不安な自分を責めずに、少し距離をとって見守ることができるようになります。
もちろん、ずっとモヤモヤしたままでいるわけにはいきません。最終的には答えを出す必要がありますが、飛びついて思考停止するのではなく、少しの間その不安に耐えながら、考え続ける。それが「コンテインメント」の意味するところです。
このように、不安に気づき、それを受け入れるという「メタ認知」がとても大切なんですね。そうしないと、私たちはすぐにディスパーサル――つまり逃避の方向に走ってしまいます。そう考えると、ネガティブ・ケイパビリティは「知的な寛容さ」とも言えますし、ある種の“大人の力”とも言えるかもしれません。
ー ネガティブ・ケイパビリティよりも、即断即決できる人のほうが賢く見えたり、頼りがいがありそうに感じることもありますよね。でも、そういう人が後になって「あれ?」と思われてしまうこともあるように感じます。私たちはつい、そうした“すぐ答えを出す力”に頼ってしまいがちですが、この傾向についてどうお考えでしょうか?
そうですね、どうしてもそうなりがちなのは、いまの時代や社会の構造にも原因があると思います。多くの人がいまだに「すべてを見通せるヒーロー型のリーダー」を理想としていて、そうした即断即決の姿が頼りがいのあるリーダー像として評価されやすいんです。
でも、現代のように複雑で変化の激しい社会では、どんなに優秀な人でも一人ですべてを見通して答えを出すのは不可能です。それでも「誰かが決めてくれた方が楽」という心理があるために、私たちはついヒーロー的なリーダーを求めてしまいます。結果、目の前の問題ばかりを処理して、本質的な解決にたどり着かない「モグラ叩き状態」に陥ることが多くなります。
しかも今は「タイパ(タイムパフォーマンス)」が重視され、短時間で判断・実行することが求められがちです。「ちょっと待てよ」と立ち止まって考えることが、非効率で評価されにくい風潮があるのも事実です。
でも、本当にそれでいいのでしょうか? その場しのぎの対処を積み重ねて悪化させるより、少し立ち止まってでも、本質的な解決策を探るほうが、結果的には近道になることもあります。まさに「急がば回れ」なんです。
今はまだ、どれだけ“考え続けたか”“不安に耐えたか”を評価してくれる社会ではありませんが、それでもネガティブ・ケイパビリティを発揮する価値は確かにあります。評価されにくいからといって、発揮しなくていいという話ではないと思います。

ー ネガティブ・ケイパビリティの重要性は理解できましたが、実際にそれをどうやって育て、日常や組織の中で活かしていけばいいのか――その点で悩む方も多いと思います。先生のご著書には具体的なヒントも多く書かれていましたが、あらためて私たちがこの力を高めていくために、どのような意識や行動が必要なのか、ぜひ教えていただけますか。
ネガティブ・ケイパビリティは大切ですが、実際には発揮しにくい状況も多く、個人だけで頑張るのは限界があります。だからこそ私は、「組織」「チーム」「個人」とレベルを分けて考えることが大切だと思っています。
まず組織のレベルでは、仕組み化が必要です。たとえばある大企業では、社長が「ネガティブチーム」という若手メンバーを作り、自分の決断を急がず、あえて「やらない理由」を集める役割を任せているそうです。一定期間チームに検討を任せたうえで、リスクや盲点を含めて判断する――こうした構造があることで、ネガティブ・ケイパビリティが組織内で発揮されやすくなります。
チームレベルでは、たとえば「今日はもやもや会議にしましょう」と宣言することで、あえて結論を出さず、意見や違和感を出し合う時間をつくる。あるいは、最初の15分だけ「もやもやタイム」として対話する。こうして共通言語としてネガティブ・ケイパビリティを共有することが、チーム全体の姿勢や判断の質を高めます。
個人レベルでは、たとえ周囲が理解していなくても、自分の中で鍛えることは可能です。たとえば、職場ではすぐに判断を求められても、家に帰って「あのときもう少し時間があれば、自分はどう考えただろう」と振り返るだけでも、ネガティブ・ケイパビリティは確実に育っていきます。
このように、レベルに応じた実践を積み重ねることで、誰でもこの力を少しずつ高めていけるのではないかと思います。
ー 先ほどネガティブ・ケイパビリティの起源について、詩人キーツが手紙の中でさりげなく書き残した言葉であるというご紹介がありました。そして、さらに遡ればシェイクスピアなども、この力を非常に重視していたとも言われています。つまり、私たちが心を動かされるような芸術やエンターテインメントの中にも、実はネガティブ・ケイパビリティの要素が深く関わっているということなんですね。
そうですね。キーツやシェイクスピアのような詩人・作家の例で言えば、「これはこういうものだ」と決めつけた瞬間に、文学はとても浅いものになってしまいます。キーツは、シェイクスピアはネガティブ・ケイパビリティを持っていたと述べていますが、それは自分の思い込みを脇に置き、徹底的に登場人物になりきって描ききる力。安易な結論に逃げずに、深く向き合う姿勢です。
文芸の世界では、これがまさにネガティブ・ケイパビリティとされていて、何かを極めるというのは、思考停止せず、簡単に答えに飛びつかないこと。ですから、何かを深めている人というのは、言葉を知らなくても自然とこの力を発揮している、あるいは発揮しようと努めているのだと思います。
ー ネガティブ・ケイパビリティは、まだ体系的に研究が進んでいる分野ではなく、明確なエビデンスがあるわけではありませんが、先生が多くの方々と何かを創り上げていく中で、やはり皆さんこの力を備えていると感じられるのではないでしょうか。特に、リーダーがネガティブ・ケイパビリティを持っていないと、実践の場ではなかなかうまくいかない場面も多いですよね。
そうですね。先ほどもお話ししたように、すべてを見通して早く結論を出し、周囲を引っ張っていく“ヒーロー型”のリーダー像にとらわれている方にとっては、ネガティブ・ケイパビリティは少し難しく感じられるかもしれません。でも、それだけでこの複雑な時代を本当に乗り越えていけるのか――そう考えると、やはりもう一つの力として、ネガティブ・ケイパビリティも持っていてほしい、と心から思います。
ー 私たちはこれまで、早く答えを出すポジティブ・ケイパビリティを中心に学んできましたが、これからの時代、AIに任せられる部分が増える中で、人間に求められるのは「答えを急がず考え続ける力」、ネガティブ・ケイパビリティではないでしょうか。本書『答えを急がない勇気』には、その力をどう育てるか、多くの実践例とともに綴られています。ぜひこの機会に手に取っていただき、ご自身の中にこの力を育てるきっかけにしていただければと思います。枝廣先生、本日は貴重なお話をありがとうございました!