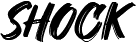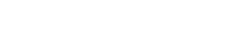
Radio Program

Tohoku, Noto, and the Path to the Future
東北、能登、そして未来へ
──地域と生きる覚悟を持つリーダーが変える!震災復興のリアルに迫る
Special Guest:FUJISAWA RETSU
スペシャルゲスト:藤沢 烈さま / 一般社団法人RCF 代表
ー 本日のテーマは「地域創生」です。社会起業家・コーディネーターとして知られ、地域創生の現場で長年ご活躍されています一般社団法人RCF代表理事の藤沢烈さんをお招きしています。藤沢さんは2011年3月11日、東日本大震災を契機に本格的に社会事業家としての活動を始められたと伺っています。
RRCFは、東日本大震災の時期に立ち上げた団体です。あれからもう14年経ちますが、今も福島の復興に関わっています。最近は福島に限らず、毎年のように災害が起きている状況ですので、全国各地の復興にも関わるようになりました。
たとえば、昨年の1月1日に発生した能登半島地震ですね。この復興にも携わっており、RCFの代表としてだけでなく、石川県が能登復興のために設立した「能登官民連携復興センター」のセンター長も兼任しています。本当にありがたいご縁をいただきながら、いろんな地域の復興支援に関わらせていただいている、そんな立場です。
ー 藤沢さんは「社会事業コーディネーター」というユニークな肩書きをお持ちですが、どんな意味が込められているのでしょうか?
「社会事業コーディネーター」という言葉には、現場で物事を前に進めるための“調整役”という意味を込めています。私は、震災復興の現場からこの仕事に入ったので、「復興をどう前に進めるか」が最初のテーマでした。
もともと私はコンサルタントをしていたのですが、現地では評判があまり良くなかったんです。アイデアだけ出して、責任は取らずに帰ってしまう、というイメージが強くて。私自身もそういう姿を横で見ていて、「この立場のままではダメだ」と強く感じたんですね。もっと現場で汗をかかないといけない、ただいるだけではなくて、実際に動かないといけないなと。
実際にやっていることは、企画を立てたり、計画を練ったり、推進のサポートをしたりと、いわゆるコンサルタントの仕事と近い部分もあると思います。でも、「社会事業コーディネーター」という名前を使うことで、より現場に寄り添って動く存在でありたい、という思いを込めています。
ー こうした活動の原点は、どこにあるのでしょうか?
そうですね、もう50歳になりますので(笑)、昔のことは少し曖昧ですが、やはり阪神・淡路大震災が原点だったと思います。私が20歳のとき、大学1年生の冬でした。当時は東京の大学に通っていて、直接被害を受けたわけではありませんが、テレビで高速道路が倒壊する映像などを見て、すごく衝撃を受けました。
あの年はオウムのサリン事件もあり、日本全体が非常に不安定な雰囲気でした。その中で強く感じたのが、「社会ってこんなにもろいものなんだ」ということ。ほんの少しのことで、前提としていたものが崩れてしまう。だからこそ、社会を支える仕事をしなければならないと、肌で感じたんですね。
当時はまだNPOや社会起業家という言葉もありませんでしたが、「社会の基盤を支えるような仕事をしたい」と、ぼんやりとでも思っていたのが原点だったと思います。

ー RCFの活動は、最初は短期で終えるつもりだったと伺っています。
はい。最初は「3ヶ月くらいやって終わりかな」と思っていたんです。コンサルの仕事を一時的に止めて、少し東北のために動いて、また戻ろうかと。実際、そのくらいの軽い気持ちでした。
100万円だけ使って終わりにしようと決めていたくらいです。その中で多少アルバイトを雇ったりもしたんですけど、「これ以上は無理だな」と思って、その金額を限度に考えていました。
ところが、ありがたいことにどんどん仕事が来るようになってしまったんです。Googleさん、キリンビールさん、資生堂さんなど、さまざまな企業と仕事をするようになって。地元のことも理解できて、企業の言語もわかって、企画を推進できる人材って、意外と少なかったみたいなんですね。
結果的に、100万円は使ってるのにまったく減らない(笑)。仕事が増えてしまって、やめるタイミングがなくなってしまったんです。今に至るまで続いているのは、まさに予想外でした。
ー 企業と地域の橋渡しのような役割もされてきたと思うのですが、印象的なエピソードはありますか?
遠くの震災時には、何百社、場合によっては千社単位で企業が関わってくださいました。ただ、残念ながら、うまくいかないことも多かったんです。
地域からは「企業は儲けに来たんじゃないか」と疑われたりすることもあって。そうじゃないんだ、と本気で思いを持って来ているんだ、ということを“翻訳”する役割が、私の重要な仕事のひとつでした。
企業の皆さんも、「社会課題に関わりたい」「地域に貢献したい」という気持ちで来てくださるんですが、その思いが誤解されてしまうことも多いんです。そうならないためにはどうすればいいのか。関わり方そのものを見直していく必要がありますし、それはとても大事なことだと感じています。
復興支援もそうですが、地域課題に関わる仕事は、どうしても行政が主体になることが多いです。でも行政には制約がある。だからこそ、企業の良さが活きる場面がたくさんあるんです。
行政は公平・平等を大切にするので、「この地域だけに支援を集中する」といったことが難しい。でも、企業ならそれができるんです。たとえば「このエリアだけ支援します」と言っても、行政のようにクレームを受けることはあまりない。それどころか、「ありがとうございます」と感謝される。行政も、そうした“尖った支援”を企業が担ってくれると、とてもありがたいんです。
ー 行政との関係性で、気をつけていることはありますか?
よく言っていたのが、「夜の復興」という言葉ですね。昼間に行政の方と会っても、公的立場があるので、本音は出しづらい。でも夜になると、違った顔が見えるんです。
行政の方ほど、地域に対して思いを持っている人はいません。ただ、制度や立場に縛られて、昼間は言いたいことが言えないんですね。でも、夜に食事をしながら話すと、「実はこういうやり方なら受け入れられる」とか、いろいろ教えてくれるんです。
行政には行政の作法があります。それを理解して動かないといけない。私たち外部の人間は、それを知った上で関わらなければならないと思っています。

ー 地域課題に関わる意義やモチベーションについて、改めてお考えを聞かせていただけますか。
まず何をやるかの前に、復興だったり、地域課題に関わることの「意義」を持っていただきたいですね。というのも、こういう取り組みは、1週間や2週間で何か形になるものではありません。まず信頼関係をつくらないといけないですし、地域もそう簡単には動かないんです。やっぱり1年、2年とかけて、じっくり取り組んでいく必要があります。
なので、そこに関わる自分自身の「モチベーション」や「意味」をちゃんと持っていないと、結局続かない。結果的に、途中で離れてしまう人も多いんですよね。
もちろん、その地域にとってプラスになることが前提ではありますが、同時に「自分にとって」「自社にとって」どんな意味があるのかも大切にしてほしいと思います。復興や地域課題への関わりが、自分のためにもなるんだという視点があるからこそ、長く続けることができる。
この考え方には、違和感を持つ人もいるかもしれません。「復興に関わるのに、自分のためにやってるの?」と思われるかもしれない。でも私は、むしろそういう意識を持っていいと思っています。地域の側からすると、「腰を据えて自分たちのことを理解してくれる人」が何よりありがたい。文化や歴史をきちんと知ってもらった上で関わってくれる人を、地域は本当に求めているんです。
だからこそ、長く関わることそのものが価値になる。そしてそのためには、自分にとっての意義も一緒に感じながら入っていってほしい。それが、第一歩目だと思っています。
ー 地域にとって継続的な価値を生み出すために、必要な視点はどんなものでしょうか。
私が復興の仕事をしてきて強く思うのは、地域が続いていくために必要な要素は大きく2つあるということです。それが、「仕事」と「教育」です。
あまりにも当たり前に聞こえるかもしれませんが、復興や地域再生の現場で長年関わってきたからこそ、結局ここに行き着くな、と感じるんですよね。
まず「仕事」。福島でも能登でも、住民の方が離れてしまったり、もともとの産業が成り立たなくなったりしています。その中で、どうやってここで働いていけるのか。これは非常に大きな課題です。
最近はどこも人手不足になっていますが、たとえば「その場所でなくてもできる仕事」しかないと、「だったら都市部でいいや」となってしまう。でも、「その地域でしかできない」「その地域だからこそ意味のある仕事」があれば、人はそこに残るし、戻ってくる可能性もある。
そしてもう一つが「教育」。これは私自身、後から気づいたことなんですが、仕事があっても、ライフステージによって人は地域を離れることがあります。たとえば結婚や子どもの誕生。そういった時に、「この地域で子育てしていけるのか」という視点がすごく大事になってくる。
医療ももちろん大切ですが、やっぱり次の世代につながるのは「教育」なんです。その地域でしか学べないこと、その土地ならではの教育があるかどうか。それが、地域が継続していくためには欠かせない要素だと感じています。
私は福島や能登で活動を続けていますが、いつも「仕事と教育をどうするか」という視点を持って、復興や地域づくりに取り組んでいます。
ー 我々もつい、課題に対して「魔法のような解決策」を求めがちです。でも、地域ごとに状況は異なり、答えを急がず、みんなでつくっていく姿勢が必要だと改めて感じました。
まさにそうなんですよね。たしかに、今後人口が減っていくのは避けられないし、地域によっては閉じていくところも出てくるでしょう。でも、その中で「やれることはある」と思うんです。
「自分が育った街を残したい」。そう思ったとき、きっと何かできることがあるはずです。答えを急がず、でも一歩踏み出して関わっていく。その中で、思いがけない出会いや、新しい価値が生まれていく。そんな未来もきっとあると、私は信じています。
ー 藤沢さんのご活動は、これからの日本の地域社会のヒントになると確信しております。本日は貴重なお話をありがとうございました!