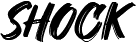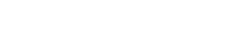
Radio Program

Hacking the Frame: Bugging Capitalism
資本主義の枠組みを意図的に“バグ”らせよ
「虫村(バグソン)」村長を直撃 新しい経済と共同体のかたちに迫る
Special Guest:NAKAMURA MASAHIRO
スペシャルゲスト:中村 真広さま / 虫村(バグソン)村長、株式会社KOU 代表取締役
ー 本日はこれからの未来を見据えるべく、新しい暮らし方を社会実装されている人物にお話を伺うため、神奈川県相模原にお邪魔しました。貨幣経済共同体のあり方を「バグらせる」という独自の発想で、未来の街づくり、村づくりを実践されています。多くの仲間とともに新しい循環を紡ぎ出し、その挑戦の舞台である「虫の村」と書き、バグソンと呼ばれるユニークな集落を訪問しました。その中心に立つバグソン村長、そして株式会社KOU 代表取締役、中村真広さんにお話を伺います。虫村を見学させていただきました。ロマンがあちこちに詰まっていますね。
ロマンで作ってるみたいな感じですからね。
ー もしかすると、このバグソンをご存知ない方もいらっしゃるかもしれません。コンセプトや、こちらに移住されてからの思いについてお聞かせいただけますでしょうか。
そうですね。バグソン自体は3年ぐらいなのですが、この藤野には4年目になります。
僕もこの場所に住んでいるので、自分の住まいでもあるのですが、やはり新しい暮らし方を通じて何か表現活動をしたいという思いがありました。一言で言うのは難しいのですが、バグソンという名の通り、この社会におけるバグのような場所を作ったら面白いと考えたんです。そのバグの作り方にはいくつかレイヤーがあると思っています。
一つは、貨幣経済、つまり経済モデルを少しバグらせること。二つ目は、共同体として一緒に住むといった、暮らし方の共同体のあり方を少しバグらせること。そしてもう一つは、今ここで収録しているこの建物もそうですが、エネルギーや水といったインフラのあり方をバグらせることです。この3つの要素を重ね合わせることで、バグを作っているという感じですね。
ー バグソンの循環する仕組みに感銘を受けましたが、これを自分でも実践したいと思っても、なかなか難しいと感じます。どうすれば取り入れられるでしょうか?
これはできると思いますよ。小さくても要素をどんどん真似ていただきたいと思っています。私も見よう見まねで実験的にやっているので、商業的にやっているわけではありませんから、どんどん真似ていただいて構いません。取り入れられるところは、それぞれの住まいや、それこそビレッジ作りをやりたい方なども、ぜひ参考にしてもらえたらと思っています。
ー 例えばテクノロジー、電気とかどうするんだろうとか。今インターネットの中にいればなかなかお仕事も難しい。この部分もしっかりと最新のテクノロジーを使われているということですよね。
そうですね。先ほどのバグの一つとして、インフラのあり方をバグらせるという点では、この建物の電気は、屋根に建材兼ソーラーパネルのものを張っているので、そこでエネルギーを自活しています。水については、その屋根面で集めた雨水を貯水タンクに溜めています。
5000リットル溜まるのですが、この建物は全て雨水を利用して動いています。しかも、ちゃんとフィルターを通せば飲み水にもなるレベルまで浄化できます。インターネットは最近だと衛星インターネットなどもあるので、有線でケーブルを引っ張ってこなくても使えるもので運用しています。この地域は、大雨などで停電になることもあるのですが、この建物だけは電力をキープできる。自律的な建物をデザインして作っているというわけです。
ー また先ほど、お手洗いに行きましたがあれも全て循環システムで、本当にびっくりしましたね。
ありがとうございます。水を使わない、コンポストトイレと呼んでいます。先ほど使っていただきましたが、うんちとおしっこ分離式になっており、うんちはおがくずと混ぜて半年から1年ほどで土に変わります。おしっこは管を通してタンクに溜め、それを薄めて使うと肥料になります。
私たちから出る排泄物も地球に還元し、栄養になるということを実践したかったのです。昔ながらのローテクノロジーであるコンポストトイレも取り入れながら、先ほどのハイテクなインフラも使っている、そのように混ぜこぜにしながらインフラを構築しているという形ですね。
ー 我々都市型生活文明の恩恵を受けているわけですが、生きる力が相当失われているな、と感じます。そして中村さんの「人を集める」というよりもバグソンに集まってくるといった、共同体のあり方もバグらせているという部分もございますよね。家賃の設定がないんですよね。
そうですね、これは無料ということではなくて利用者が言い値で値付けをするという仕組みです。新しいですよね。実は、経済学の論文などでは、消費者側やユーザー側が値付けをする経済モデルのあり方が研究されており、世の中に存在しないわけではありません。
しかし、それを不動産でやっている事例は見かけませんでした。これは実験してみても面白いのではないかということで、今まさに実験を始めている最中です。

ー 相模原のバグソンプロジェクト。本当に賃料を設定しないというすごい画期的なことをされていますが、その中で感謝経済というキーワードがあったと思います。これについてもう少し深掘りさせていただきたいのですが、賃料以外にも何か他に取り組まれていることはありますか。
そうですね。感謝経済というのは造語ではありますが、まさに商品に値付けがされていて、お金を払えば価値を得るという関係性ではなく、もう少し循環するモデルで経済モデルを作れないかと思った時に、無限に増殖できるものの一つが感謝の気持ちだと思ったんです。お金には元手がいりますが、感謝の気持ちは、自分の感度を高めれば増やせますよね。「今日も晴れててありがとう」「今日も雨降ってくれてありがとう」「この場所をきれいにしてくれてありがとう」といった気持ちは、気づかなければ生まれませんが、気づけると無限に湧いてくるものです。しかも原価はゼロです。
ですから、感謝が巡るということは、元手がいらず、しかも人と人がつながれる一番のツールになるのではないかと思っています。この場所自体もそうですが、私たちはさまざまな自然の恵みで成り立っているわけです。本来、私たちは生かされている存在であるはずなのに、都会にいるとそれに気づきにくい。私たちは最初から「ギフト」を与えられまくっています。私がこの地に住み始めてから気づけるようになりました。同じことをこのコミュニティの中でも回せたらどうかというところでこの概念に至りました。
例えば、太陽や雨などからギフトをもらっています。バグソンというプロジェクト自体は、ある意味、私個人がファーストギバーとして場を作っているのかもしれませんが、それを自分の所有物だからといって切り売りし、「このぐらいの賃料で」とお商売にするのではなく、一旦与える。
受け取った人が感謝の気持ちがあれば、家賃として払ってもいいかもしれないし、あるいは一緒に道を作る、森の整備をする、といった形でギフトし合ってもいい。それはもう感謝の気持ちによるものでいいのではないか、というモデルが感謝経済という概念です。
ー 感謝経済について、都市部や地方で取り入れたいと考える読者へ向けて、このプロジェクトを始めたきっかけや、実践への具体的なヒントをお聞かせください。
家賃を完全に入居者に委ねるというのは、かなりエッジケース(極端な事例)だと思うんです。
もう少しマイルドなケースは作れると思っています。例えば、賃貸のオーナーさんだとしたら、「基本家賃は5万円に設定しますが、これは最低ラインなので、プラスアルファのアドオンはご自由にどうぞ」といったように、バッファーを作る。感謝の気持ちで上乗せできる余地を作るわけです。最近のクラウドファンディングのように、応援経済とも言えるかもしれません。
感謝経済は私の造語ですが、自分の気持ちを経済に載せて流通させられるというあり方は、もう少しマイルドなパターンもあると思います。例えば、そういった形でやってみるのも良いかもしれません。自分が価格設定したものと100%一対一対応で経済モデルを作るのではなく、少し揺らがせるあり方は存在するはずです。
ー この「バグ」という概念が広がっているのを感じますが、中村さんの現在の仕事や経済活動について詳しくお聞かせください。成功者だからできるのではなく、誰もが一歩踏み出せるヒントをいただけると嬉しいです。
ありがとうございます。私は資本主義から足を洗って仙人になっているわけではなく、今もベンチャーを続けています。以前、TSUKURUBAという会社を共同創業・共同代表として上場させましたが、そこを退任し、また新しくベンチャーを作ったりしています。
こうしたビジネスを今もやっています。資本主義を否定してバグソンのような活動をしているわけではなく、ゲームが違うと思っているんです。世の中の全てが資本主義ゲームに染め上げられてしまっているのが現状だと感じており、そこに対して一石を投じる意味でバグを作っているという感覚です。とはいえ、大半の99.9%は資本主義的な世界で成り立っていますから、それを否定はしませんし、そのパワーをうまく活用して世の中にインパクトを出すこともできると思っています。
ですから、ベンチャーを経営して日々プロダクトサービスを作るということもやっています。そしてもう一つは、この地に移り住んでローカルエコノミー、つまり地域の中で、駅前にカフェを仲間と作ったり、写真館を仲間と作ったり、地元の思いある仲間たちと一緒に場を一つ一つ作っていくということをやり始めています。これはローカルの中で経済を回していく活動です。都心の資本主義の動きからすると緩やかなのかもしれませんが、地域の経済活動に合うようなリズム感で地域エコノミーを作っていく。これもやっています。
私は三股しているような状態です。バグソンで非営利な暮らしを通じた表現活動、ローカルエコノミーという少し緩やかな資本主義的な活動、そして三つ目として、資本主義のど真ん中であるスタートアップの中で会社を作り経営をするということをやっているという感じです。

ー TSUKURUBA時代から「場作り」を追求されてきた中村さんですが、こちらに移住されてから、アイデアや発想の「シャープさ」に変化はありましたか。
ありますね。自分のメンタル的な部分が非常に整います。フィジカルもメンタルも整うというか。都心にいると「体を動かさなきゃ」とジムを契約したりしますが、森に入って木を切ったりといった作業をするだけで、良い筋トレになるわけです。この地で生活すると体も動かすし、草刈りなどをやった15分後にオンラインミーティングをしたりしています。
パッとジムに行って帰ってきて仕事をするのと、やっていることはほぼ一緒です。しかも、それがフィジカルに目に見える形で影響を与えている。この土地にいると心と体が整ってきたなというのはあります。あとは、東京を離れて地方に行くことで、東京では見えてこなかった側面がたくさん見えてきます。特にこの地に来て思ったのは、地域を作るのは東京のイケてるベンチャーなどではなく、この地場の、個人でやっている方々や地元の中小企業、中堅企業の方々が、それぞれの思いを持って街を作っているんだということです。
そういった事業継承をされている方々に対し、もっと価値提供できるものはないか、というのがビジネスのアイディアの切り口として見えてきたのは、こちらに移ってきた一つの変化かもしれません。
ー 働き方や日本企業のあり方、持続可能性といった点で、資本主義経済からの脱却ではない、一つのきっかけを作っているという印象を受けます。リスナーの皆さんも、パソコンやホームページでは伝わりきらない「できていること」を、ぜひ一度現地で肌で感じ、ご自身のあり方を考えるきっかけにしてほしいです。
ここは暮らしの場所、家なので、なかなか見学ツアーなどはやってなくてですね。リスナーの皆さんが見聞きするには、記事などで伝わることになるかもしれません。ありがたいことに取材もしていただけるので、こういう考え方だけでも伝わっていくと良いのではないかと。
「こういうバグの村を作ってるやつがいるらしいぞ」というだけでも、じゃあ「俺もやってもいいのかな」というヒントになると良いなと思っています。
ー 中村さんの周りに人が集まる空気感は、TSUKURUBA時代から元々お持ちだったのか、あるいは何か象徴的な出来事がきっかけとなったのか、その原点についてお聞かせいただけますでしょうか。
そうですね。昔から、何か自分でことを起こしてみるということは好きな方だったとは思うんですけど、最近言語化できてきたのがあって、やっぱり人の内側にある衝動というものが一番大事だと思っています。僕は冗談半分でセルフブラック企業って言っているんですけど、誰かから言われて渋々やっているとリアルブラック企業ですが、自分自身でやりたくて、24時間そのことに向き合っているのは、めちゃくちゃ健全ですよね。誰に言われているわけでもないから残業でもなんでもないという話です。
そうした状態になれるためには、自分の衝動に忠実に生きているかどうかが大切だと思っています。私は今、3つのレイヤーの活動を全てやっていますが、これもやりたいからやっていて、誰にやれと言われたわけではありません。そうすると時間はそれぞれに使って、日々てんてこまいではあるんですけれど、すごく楽しいんです。
やはり、そういうふうに衝動で生きている人が周りにいっぱいいたし、仲間からもエネルギーをもらえるので、少しずつ自分の人生を生きている人が増えていくと、周りも影響されて世の中が活性化していくと思うんです。私はそういう火種の一人になりたいという気持ちがあるし、
まさに自分の人生を生きることを支援するというものを、今僕がやっているベンチャーでやったりもしているという感じですね。
ー 現在されている様々な取り組みの中で、中村さんが特に大きな学びを得た実験や経験があればお聞かせください。
それこそ先ほどのマネジメントの話でいくと、この「木」の構造と「組織」の構造がシンクロするのではないか、という大きな気づきがありました。
例えば、週末に森の作業を教えていたのですが、森に入ってどの木を残し、どの木を切るかを選別する際、林業をされている方々と一緒に作業すると、それぞれ視点が違うのです。「この木はどう思う?」「上が塞がれているから、あまり伸びないかもしれない」「では、これは切りますか?」といった議論が生まれます。すると、「いや、ちょっと待とう。周りの老木を切り、この若手を伸ばす方がいいのではないか」という意見が出る。これこそ、まさに組織論だと感じたんです。
森を見ながらどれを残し、どれを切るのか。組織でも上が詰まると若手が伸びないという状況があります。上の人たちを解雇するというよりは、適切に退職して次のポジションに移ってもらうことで、若手が育っていく。これ、まさに森と同じなんですよね。この気づきは森に入っていて得られました。非常に面白い発見でした。
他にも様々な学びがありますが、ローカルエコノミーの方では、地元の仲間たちと場を作る際、彼らもそれぞれ内なる衝動を持っているんです。「いつかこういうことをやってみたかったけれど、きっかけがなかった」という人に対し、私たちがきっかけの入り口を一緒に作り、「こうやればできるんじゃないですか」と提案すると、その人はいきなり輝き始めます。自分の人生を生き始めるというか。そういう人たちと一緒に場を作っているので、主人公はそれぞれなんです。私は下支えする役目です。
強烈な資本投下やカリスマ的なリーダーシップで街を変えていくのもかっこいいですが、実際はそうではなく、個々人が輝いている街の方が絶対に素晴らしい。私たちはそういう街づくりを目指しています。やはり、主人公を作っていく、それぞれの主人公を作るということに気づきもあります。「こうやって人の心に火がついていくんだ」というところを、一緒に場を作りながら日々体感しています。
ー 現在、非営利のコミュニティサービス(バグソン)、ローカルコミュニティ、スタートアップのベンチャーという三本柱で活動されていますが、バグソンの運営が、他のスタートアップやローカルサービスに与えている良い影響についてお聞かせください。
バグソンが存在することで、非常に多くの方とつながることができています。私自身が最も衝動を込めて作っている核となるプロジェクトがバグソンなので、地域の方々からも「バグソンをやっている中村」と認識されるようになりました。
その結果、「バグソンの中村」という視点を通じて、様々な方とつながりを持つことができるのです。以前お話しした思いを持った地元の仲間とも出会え、新しく地域に活動の場が生まれるきっかけにもなっています。
さらに、バグソンは層を超えた影響を与えています。例えば、バグソンの長屋に住む住民の一人は、元々ベンチャー企業で勤めていた方ですが、バグソンでの暮らしを通じて「転職したい」という相談を受け、私が知人のベンチャー企業を紹介し、実際に転職に至ったケースがあります。
このように、バグソンでの暮らしという表現活動のレイヤーから、スタートアップのレイヤーまでを横断するような住民もいます。各層で分かれているように見えますが、実際には様々なところにパス(繋がり)が生まれているというのが現状です。
ー 人と自然、そして経済が循環する新しいあり方を教えていただきました。本日は貴重なお話をありがとうございました!