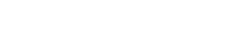
Radio Program

Who Makes Us Laugh — AI or Humans?
笑いをつくるのはAIか、人か
──“お笑い×テクノロジー”の現在地と創造の再定義
Special Guest:TANAKA SOTA
スペシャルゲスト:田中 爽太さま / 株式会社FANY テクノロジー開発部 プロデューサー
ー 本日は「生成AIとお笑い」のクロスイノベーションをテーマとして取り上げてまいります。本日のスペシャルゲストは、株式会社FANY テクノロジー開発部 プロデューサー 田中 爽太さんです。FANYさんといえば、チケットサービスを思い浮かべる方も多いと思いますが、実際にはチケットだけにとどまらず、次々と新しい挑戦をされている会社ですよね。
そうですね。もともとFANYというのは、弊社吉本グループが劇場をたくさん持っていますので、そこのチケットサービスというところから始まりました。
ただ、コロナ禍になって劇場が閉鎖されてしまい、生配信やオンライン配信を見ていくことになった時に、吉本興業としてデジタルプラットフォームなどのサービスをしっかり盛り上げていかなきゃいけないというところで、そこをきっかけにFANYというところで一つ統合されたというものになっています。まさにいろいろとチャレンジしていこうというようなところではあります。
ー その挑戦の一つが、生成AIの活用ですね。FANYさんは「ユーモアを理解するAI」という切り口で、生成AIを活用した取り組みを進めていらっしゃいます。お笑いは、ツッコミやオチ、間といった要素が重要で、非常に個人的なセンスや俗人性が際立つ世界です。その領域に生成AIは本当に活用できるのか。まずその点について伺いたいと思います。
やっぱりここの「ユーモアを理解する」っていうところは、まだまだできているわけではなくて、これから「何を今できていて、何ができていないのか」っていうところとか、あるいは「これがどういうビジネスに活かせていけるのか」っていうところは、まさに模索しているような状況かなとは思っています。
ただ、生成AIのようなものが出てきたときに、少し昔の話になりますが、やっぱりエンタメって、もともとは寄席小屋から始まって、それがラジオで全国に広がって、テレビができてテレビスターが生まれて、さらにYouTubeになってYouTuberが出てきた、というように、テクノロジーの進化とともに形が変わってきたと思うんですね。
そう考えると、「これをAIでどう遊べるのか」とか、「自分たちの事業はどう変わっていくんだろう」というところは、まずはいろんなことを試してみよう、というところから始まっています。ユーモアを理解する、というのも、これまで言語化できてこなかった部分でもありますし、ある意味、避けてきた部分でもあるので、まずは面白がりながら、やってみている、という状況です。
ー AIがお笑いまでできるとは驚きです。「AI創作落語」や「AI漫才」といったAIエージェントのプロジェクトに取り組もうと思われた、その経緯を教えていただけますか?
もともと私が新規テクノロジーとエンタメを掛け合わせて「新しいことどういうことできるか」というところを担当している中で、メタバースの時もそうだったんですが、実は芸人さんがすでにやっていて「これ実用できるんじゃないか」みたいな話が出てきたりだとか。生成AIが出てきたタイミングでも、すでに芸人さんが使っていたりしたんですね。
やはり、そういった周りの動きを見ながら、「まずはいろいろやってみよう」となったのが経緯といいますか。
エンタメ事業というか、我々の会社には新しいことができたら「とりあえずやってみよう」「何でもいいからやってみよう」というところがありますので。まさに生成AIが出てきたタイミングで「どんなことができるのかな」「タレントさんをAIでどうサポートができるのかな」と、やれるところから進めていき始めた、というところではあります。

ー 桂文枝師匠がGoogleのGeminiを活用し、「桂文ジェミ」という高座名まで命名された創作落語プロジェクトも話題になりました。こちらの手応えはいかがでしたか?
そうですね。やはり、あれだけの師匠がやられるということは、外部の方もそうですし、社内を含めてですね。若手や中堅の芸人さんに「こんなことができるんだ」という気づきを与え、やはり、そういうモチベーションアップにつながっていく部分があったのかなと、非常に思っています。
ー AIが学習して成長していくとはいえ、お笑いやタレント性といった「個人の資質」は標準化が難しい領域だと思います。 一般的なビジネス活用とは異なる、エンターテインメント分野ならではの社会実装について、どのようなイメージをお持ちでしょうか?
まさに、そこがこれからどうなっていくのか、というところで、我々自身も悩みどころというか、苦悩している部分ではあるんですが、たとえば桂文ジェミのプロジェクトのようなものを見ていると、このAIというのは、芸人さんであったり、プロの方々、いわゆるプロフェッショナルの人たちを、より飛躍させるものになり得るんじゃないか、という感覚があります。
これまで創作落語というのは、文枝師匠も本当にたくさん作ってこられていて、「もっと作りたい」「500作くらいは作りにいきたい」とおっしゃっている中で、実際には1カ月に1本作れるかどうか、というペースだったんですね。そこにAIの力を借りて、「こんなアイデアはどうですか」といったものをどんどん出していくことで、1カ月に2本、3本と作れるようになる。
そうやって、コンテンツのクオリティであったり、あるいは量というものを、AIがサポートできる。これは、すごく大事なポイントだと思っています。
分かりやすく言うと、いま活躍している芸人さんや、プロのクリエイターの方々とAIをどう組み合わせるか、というところが重要で、逆に言うと、AIがなければそこまでの量や広がりを作りにいけない、という状況も出てくるのかもしれない。
そういう意味では、ある種、二極化していく部分もあるのかな、というふうにも思っていて、少なくとも「使わない」という選択肢は、だんだんなくなってきているのかな、という感覚はありますね。
ー 生成AIを活用することで、すでに高い才能を持つプロの方が、これまで以上に多くの質の高い作品を生み出せるようになり、私たちもより多くの新作を楽しめる、ということですね。
そうですね。やはり、プロの方々は、より新しいものをどんどん生み出せる、ということが、この桂文ジェミのプロジェクトを通しても分かりましたし、こうしたことを繰り返していく中で見えてくるのは、ある意味、自分で「作りたい」と思っても、どう作ったらいいのか分からない人たちがたくさんいる、ということでもあると思うんです。
そういう一般の方々が、こうしたAIを活用して、たとえば私たちが言っている「ユーモアを理解できるAI」のサポートを受けることで、日常の生活が少し面白くなったり、あるいは自分でちょっとした面白いことができるようになっていく。
そうやって、コミュニケーションがより豊かになっていくということが、「お笑い×AI」という取り組みにはあるのかな、と、すごく感じていますね。
ー 生成AIの進化が非常に速い中で、FANYさんの最新の取り組みの中で、いま直面している課題や、まだ踏み込めていない領域があれば教えていただけますか。
ありがとうございます。
まさにそのあたりが、いま一番悩んでいるところでして、本当にAIの進化があまりにも速いんですよね。かなり大きな企業でも、ある程度はAIだけでできてしまうような状況になりかけている中で、これまでであれば「コンテンツを作ろう」となったときに、そこに投資して、数カ月かけて作る、ということが当たり前でした。でも今は、「あれ、これもうできちゃうじゃん」ということが起きてしまう。
そうなると、どこに時間やお金、リソースをかけていくべきなのか、というのがすごく難しくなっています。これはきっと、他の会社さんも同じだと思います。どこで勝負していくのか、というところですね。
その中で、我々のところで言うと、芸人さんのサポートをしたり、芸人さんの活動を広げていく、ということはできるんじゃないか、という感覚はあります。文枝師匠がAIのサポートによってご自身の活動をより広げていく。あるいは、先ほどのかまいたちAIのように、これまでできなかった「本人としゃべる」ということが、24時間365日、時間や空間を超えてできるようになる。そういう価値は、すごくあると思っています。
ただ、それも誰でも作れてしまうようなものになってきたときに、「タレントとAI」をどう考えればいいのか、という問題が出てきます。AIは自動化や効率化の方向にどんどん進んでいく一方で、タレントというのは、「この人だから聞きに行く」「この人だから見たい」という希少性が価値です。そこにAIの効率化が、そのまま当てはまらない部分もある。
じゃあ、このAIを使って、どういうビジネスを作っていけるのか。そこは、正直言って、まさに今すごく難しいところだと感じていますね。

ー Google AI Studioなどで誰でもアプリを作れる時代の中で、今後FANYとして、芸人さんやAIをどう活かした展望を描いているのか、教えていただけますか。
ある意味、最初にAIが出てきたときに、すぐに取り組めたこと、実際にやってきたこととしては、まず「タレントのAIを作る」というところからでした。田村淳さんのAIだったり、EXITさんのAI、かまいたちの「かまいたちAI」など、まずはそういうところから始めていきました。
それによって、タレントさんが普段は時間や場所に縛られている中で、AIによって、もう一つの自分の分身が別の場所で働いてくれるんじゃないか、という考え方で取り組んできた部分があります。
ただ、そうしたことをやっていく中で、逆に「だからこそ価値があるんだな」と思ったのは、ファンの方々は、ある程度AIも楽しみつつ、やっぱり最後のところでは、「本人が何を言ったのか」とか、「その人がどういう文脈で活動してきたのか」というところを見ているんだな、ということでした。このAIタレントを作っていく過程で、改めて「ファンは生身の人間についている」ということに気づかされたところでもあります。
こうした生身のリアルな部分というのは、AIがどんどん広がっていくほど、むしろより貴重で、より価値のあるものになっていくんだろうなと思っています。
一方で、AIによって単価が下がっていく領域も出てくるでしょう。だからこそ、我々のところで言えば、タレントマネージャーやマネジメント、ライブといった、すごくコアな部分を、これまで以上に突き詰めていく必要があるんだろうな、と感じています。そうなったときに、「じゃあ自分は何の仕事をすればいいんだろうな」と思うことも正直あるんですが、逆に言えば、AIを試してみたからこそ気づいたのは、「やっぱり生身の人間にしかできないことって絶対にあるよな」ということでした。
ー AIが便利になるほど、生身の人間の才能やストーリーの価値がより重要になる、ということですよね。ビジネスの世界も同じだと思いますが、いかがでしょうか。
やっぱり、どんどん「誰でもできちゃう」時代になってくると、自分自身のノウハウだったり、自分がこれまでやってきたことが、すごく大事になってくるんだろうな、というのは感じています。先ほど大川さんがおっしゃっていたように、Google AI Studioなどを使えば、誰でも作れる時代になってきているわけですよね。
その中で、うちのところには野田クリスタルという、M-1の漫才のショーレースでも活躍している芸人がいるんですが、彼はもともとゲームが好きで、自分でプログラミングしてゲームを作っている人なんです。実際にアプリでゲームを作ってみて、「こんなにどんどん作れるんだ」ということに本人もすごく驚いていました。
そうなってくると、その人ならではの独創性を持ったゲームが生まれてくる。誰が作って、どういう考え方で作っているのか、というところがすごく大事になってくると思いますし、そういうものがどんどん出てくることで、逆にコンテンツ業界全体もすごく盛り上がっていくんじゃないか、というふうに思っています。
ー 野田クリスタルさんの「スーパー野田ゲーメーカー」や野田AIのように、今後はM-1のネタなどもAIで作れるようになりますね。今までスキルがなくて諦めていた人でも創作が可能になり、誰にでもスターになるチャンスが広がったと言えるのではないでしょうか?
「こういうこともできそうなんだ」「あ、これ自分でもできるんだぞ」と感じてもらえるところが、すごく広がっていく可能性があるんじゃないかなと思っています。
そういう使われ方がどんどん増えていく中で、我々としても、そうした人たちをどうサポートできるのか、ということを常々考えているところですね。
ー 2040年ごろを見据えて、生成AIやテクノロジーの進化の中で、エンターテインメントやFANYがどんな姿になっているとお考えか、田中さんが描いている未来像を最後に教えていただけますか。
なかなか難しいな、と思っています。正直なところ、いまは私たち自身も、「作っていくことで何が見えてくるんだろう」というところを、まさにやっている最中なのかな、という感じですね。
その中で一つ思うのは、たとえば翻訳のAIを作ることで、言語の壁がどんどん破られていって、誰でも世界に発信できるようになりつつある、ということです。お笑いもそうですし、これまでは国内だけだったり、言語の壁が大きくあった分野が、AIによってどんどん広がっていく。音楽だけでなく、いろいろな分野で、自分たちが作ったクリエイティブなものが世界中に広がっていく。しかも、それがどんな人でも、よりクオリティの高いものを出せるようになっていく。ある意味、誰もがスターになれるような未来が来るんじゃないか、というふうに思っています。
そうした未来に対して、我々として何ができるのか。未来のスターをどうサポートしていけるのか。そこに関われるようなことが、今後できていくといいな、と考えているところです。
ー SNSやYouTubeが新しいタレントを生み出してきたように、生成AIもエンターテインメントを大きく変えていく存在になりそうです。今日はその未来の一端を垣間見ることができました。まだ始まったばかりの挑戦ですが、これからの展開を引き続き見守っていきたいと思います。本日はありがとうございました!




